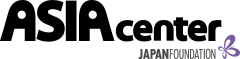「ASIA HUNDREDS(アジア・ハンドレッズ)」は、国際交流基金アジアセンターの文化事業に参画するアーティストなどのプロフェッショナルを、インタビューや講演会を通して紹介するシリーズです。 文化・芸術のキーパーソンたちのことばを日英両言語で発信し、アジアの「いま」をアーカイブすることで、アジア域内における文化交流の更なる活性化を目指しています。
フランスとラオス、それぞれのヒップホップ・カルチャー
武藤:少なくともダンスに関して、これまでラオスと日本の交流はあまりなかったように思います。ぼく自身、ラオスの方とお会いするのは今日が初めてかもしれません。どういったきっかけで今回の来日に至ったのでしょうか。
オレ:2015年の「DANCE DANCE ASIA」ツアーがきっかけです。12月にビエンチャンで公演があったんです*1 。ちょうど私達が毎年開催している国際ダンス・フェスティバル「ファン・メコン・インターナショナル・ダンス・フェスティバル(Fang Mae Khong International Dance Festival)」 *2 が終わったところだったので公演を見ることができました。そこで国際交流基金アジアセンターの皆さんと出会い、TPAM 2016- 国際舞台芸術ミーティング in 横浜に招へいしていただいたわけです。
*1 「DANCE DANCE ASIA―Crossing the Movements」は国際交流基金アジアセンターおよび株式会社パルコによる主催・企画で、ストリートダンスを軸にアジア地域内の交流と共同制作を支援するプロジェクト。2015年1月から各都市で開催されている。同年12月のビエンチャン公演では、日本からHilty & Bosch、Memorable Moment、AREA ROCK STYLERが出演、ワークショップも行った。
*2 カンパニー・カムとファンラオ・ダンス・カンパニーが主催する、ラオスで初めての国際ダンス・フェスティバル。2010年に設立され、ほぼ毎年開催されている。
武藤:「DANCE DANCE ASIA」にも参加したのですか?
オレ: はい、ファンラオ・ダンス・カンパニー(Fanglao Dance Company)として、『ファン・ラオ(Fang Lao)』という新作の一部を上演しました。
武藤:「DANCE DANCE ASIA」はいかがでしたか?
オレ:ラオスではこうしたダンスのイベントは多くありません。海外からダンサーがやってきて上演をするとか、地元のダンス・シーンに何かをもたらしてくれるということ自体が刺激的なのです。ビエンチャン公演では、日本から3組、ラオスからファンラオともう1組が出演しました。表現の方向が多彩で、とてもバラエティに富んでいましたね。有名なダンサー2人組のストリートダンサーがいました。
武藤:Hilty & Bosch*3 でしょうか。
*3 1997年に結成された、JinとYouの2人組。ロッキングを軸として世界的な名声を誇る。
オレ:世界的に有名な人達ですよね。ほんとうに多彩で楽しかった。ブレイクダンスだけでなく、コンテンポラリー、ジャズなどもありました。ラオスでは、伝統舞踊とブレイクダンスの2つが発達しているのですが、コンテンポラリー、バレエ、ジャズはありません。とても興奮しましたよ。

武藤:オレさんはフランスが拠点ですよね。いつからお住まいなのですか?
オレ:2歳の時、つまり1980年からリヨンに住んでいます。母親が姉と私を連れてフランスに移住したのです。父親はラオスに残りました。
武藤:リヨンにはラオス系住民が多いのでしょうか?
オレ:リヨンもパリも多いですね。ラオスはフランスの植民地でしたから、彼らが去った後に色々なものが残っています。フランスパンもありますし、ペタンク(フランス発祥の球技)などはラオスの国技になっています。
武藤:国技なんですか!?
オレ:信じられないでしょう?(笑)
武藤:お母様はどうしてフランスへ移られたのですか?
オレ:当時の政治情勢から、子どもをラオスで育てるのは良くないと判断したようですね。どちらかというと自分はラオス人というよりフランス人だと思います。しかし親族の一部は故郷で暮らしていますから、ラオスの文化や人々には強い興味があります。だから2006年以来、ラオスに足を運んでいるのです。年に3回ほどでしょうか。とはいえ、休暇を過ごしに行くわけではなく、色々なことを共有したくて出かけるわけですが。私はダンサーで振付家ですから、ラオスのアーティスト達と継続的な関係を築こうと考えたのです。
武藤:ダンスに出会ったのもフランスですか?
オレ:ええ、ご多聞に漏れず、マイケル・ジャクソンがきっかけです。マイケルの真似をしていました。そこからもっとダンスのことを知りたいと思うようになったのです。最も身近なところにあったのがヒップホップ・カルチャーであり、ストリートダンスでした。確か14歳の時だったと思います。家の近所でもやっている人がいて、お金もかからないので習い始めました。ブレイキング、ロッキング、ポッピングといったオールド・スクールですね。今はストリートダンスのニュー・ジェネレーションというものがありますが、私の世代はやはりオールド・スクールのストリートダンスです。そこからさらにダンスを広く学びたくなり、フランスやイタリアのコンテンポラリーダンスのダンサーや振付家に習うようになりました。2006年からはカポエィラも習っていますし、ラオスの伝統舞踊やタイのコーン(古典仮面舞踊劇)も習っています。
武藤:ストリートダンスを始めた当時、周りにも仲間が大勢いたわけですか?
オレ:いましたね。最初は先生がひとりだけで、その周りに集まって習っているだけでしたが、やがて自分達でテクニックを追求し始めたりもしました。フランス人、ラオス人だけでなく、アラブ系、アフリカ系など色々な人がいましたね。外国人の多い地区だったのです。公民館とか、店の裏とか、駅とか、平らな床があるところならどこでも練習していました。

武藤:多国籍的な環境のなかで、ヒップホップ・カルチャーがいわばひとつの共通言語になっていた、といっても良いでしょうか?
オレ:初めはそうだったと思います。リヨンで共生している人々の共通言語ですね。しかし今はもっとシーンが大きく、さらに開かれたものになっています。ヨーロッパのヒップホップ・シーンは、アジアとはかなり違います。もともとヒップホップ・カルチャーは、アメリカで「不良」の文化として生まれてきたものですが、暴力ではなく芸術的なバトルで闘おうという方向へのシフトが起きてきたわけですよね。縄張り争いなどにしても、ダンスとか、歌とか、グラフィティとかでバトルをする。それからおよそ10年後に、ヒップホップはフランスやヨーロッパにもやってきました。ここでもやはりコミュニティにおける表現の手段として、人々はヒップホップを用いました。文化が社会的な意味を担ったのです。社会問題、人種問題、排除の問題。排除された人々のコミュニティでヒップホップが流行します。ヒップホップにはダンスやグラフィティ、ラップや音楽など様々な表現手段がありますから、たくさんの人がそこに自分なりの表現を見出せるのです。
他方、アジア、たとえばラオスでは、若いダンサー達は表現のためにブレイクダンスをやっているわけではありません。ただカッコいいからやっている。ヘッドスピンとか、派手な技がありますし、アメリカ文化そのものが「カッコいい」わけです。いつも何か新しい表現を求めていますからね。アジアでは若者達の問題はもっと別のところにあります。私が初めてラオスを訪れてストリートダンサー達に会った時、若者達がみんな裕福な家の子ども達だということに気づきました。なぜでしょう。貧しい家の子どもはストリートダンスを練習する時間などないからです。インターネットで何かを学んだりすることもありません。これは大きいなと思いました。
武藤:ヨーロッパではヒップホップはいわば社会的弱者の文化であるのに対して、アジアでは富裕層の所有物だと。
オレ:ただ徐々に変わってきています。色々な世代や層に支持され、とても開かれてきていると思います。ヨーロッパでは、都会でも田舎でもどこでもヒップホップ・シーンがあり、ストリートダンスをやっていますが、ラオスのストリートダンス、ヒップホップ・シーンはかなり違っていて、私達も最初は富裕層のダンサー達と作業をしていました。やがて、あらゆる層の人々と一緒にやりたいと考え、学校の授業にストリートダンスを取り入れるよう働きかけました。学校なら、家が裕福でも貧しくても、子どもはみんな通いますから、社会全体と接点が持てると考えたわけです。たとえば中南部カムムアン県にあるターケーク郡では、5つの学校で毎年ワークショップを開いています。6ヶ月間、毎週教えて、学期末の3月にはコンテストを開催しています。
武藤:自治体や学校とはどのように交渉したのですか?
オレ:ターケーク郡の場合は、フランスのある地域と協定*4 を結んでいたので、フランスの私のカンパニーを比較的簡単に受け入れてもらえました。しかし最初は支援などありませんでした。協定では、教育、灌漑、医療などの分野しか想定されていなかったからです。学校でのストリートダンスを用いた活動を説明し、また生徒達が関心を持っている事実を伝えたところ、理解してもらうことができました。こうして今では文化交流もプログラムの一部になっています。フランスとラオスの各自治体から助成も受けています。両者の関係があったからこその成果でしょう。政治から何かが生まれることもあるのですね。
*4 フランスのローヌ=アルプ地域圏議会とラオスのカムムアン県とが締結した協定。地方自治体における教育、保険医療、文化交流、水資源、ジェンダー格差などの課題強化と改善を目的としている。


伝統舞踊とブレイクダンス
武藤:冒頭でオレさんから「ラオスでは伝統舞踊とブレイクダンスの2つが発達している」と伺って、とても興味深いと思いました。古いものと新しいものが共存していて、これらをおふたりはコンテンポラリーダンスという文脈によってつないでいるという理解でよいでしょうか?
ヌーナファ(以下ヌート):私の場合は、6歳の頃から学校でラオスの伝統舞踊を習っていました。ヒップホップ・カルチャーに出会ったのは15歳、2005年ですね。しかし当時ラオスで知られていたのはBボーイ、ブレイクダンスだけで、ヒップホップ・カルチャーのことはよくわかりませんでした。Bボーイのことをヒップホップとも呼んでいたんです。実際に踊り始めたのは、オレがラオスに来てからです。ワークショップで色々なスタイルを教えてくれました。同時にコンテンポラリーも習いました。私にとっては、「コンテンポラリーダンス」とはすなわちオレのことです。「ファン・メコン・インターナショナル・ダンス・フェスティバル」を創設したのも彼ですし。

オレ:ヌートと出会ったのは、ビエンチャンにレジデンシーしている時のことです。アンスティチュ・フランセが地元のダンサーと一緒に作業をする1ヶ月のレジデンシー・プログラムに私を招いてくれて、特にブレイクダンスのダンサー達に、ブレイクダンスとコンテンポラリーダンスを教えました。若者達に、テクニックを向上させつつ、異質なジャンルをかけ合わせる手法を知ってもらうのが目的でした。たとえば、ヒップホップ・カルチャーとラオスの伝統舞踊をかけ合わせて現代的な作品をつくるといったことです。
武藤:ダンスを社会のあらゆる層に普及させていく取り組みについて先ほど伺いましたが、たとえば伝統舞踊ではそうしたことは考えられなかったのでしょうか? かつては伝統舞踊が社会のなかで一定の機能を担っていたと思います。それはやはり衰退してしまって、ストリートダンスがその代わりになるということなのでしょうか?
オレ:いえ、そうではありません。これは政府の役人達にも説明する必要があることなのですが、私達は伝統舞踊をストリートダンスに置き換えようとしているわけではないのです。ただ若者達が新しい表現手段に関心を持っているということを説明しました。同時に、異なったものを組み合わせ、一緒にやっていくことができることも話しました。
武藤:両方が共存しているわけですね。
オレ:そうです。学校で教えたり、ダンス・フェスティバルをする時も、ラオスの伝統舞踊も上演しています。
武藤:社会的機能という面から見て、伝統的な舞踊とストリートダンスの違いは、どのあたりにあるといえそうでしょうか。
オレ:かつてストリートダンスは海外から来た好ましくないものだというイメージがあって、役人とか、大人達の間では評判が悪かったのです。ところがストリートダンスには若者が熱中する、そしてストリートダンスに熱中している若者は悪いことに手を出さない、という認識が出てきました。たくさんの若者がストリートダンスを楽しんでいるのを見て、政府も容認し始めました。スポーツと同じように、ストリートダンスは若者の善導につながるのです。
ヌート:父兄や役人達をイベントに招待して、プロのダンサーになるにはどうするのか、どんな訓練を積むのかを見てもらいました。
オレ:ダンスは創造性、協調性を育てるのに良い方法です。10人もいればグループをつくれますから、放課後、一緒に練習して、私達がやっているようなイベントに出演するわけです。若者達がダンスを練習し、発表する機会をつくるためにフェスティバルをやっています。
武藤:かつての伝統的な社会で民俗舞踊が果たしていたのと似た役割を、ストリートダンスが担うということかもしれませんね。

- 次のページ
- フェスティバルの運営と、国際的なコラボレーション