テクノロジーで追及するダンサーの思考と身体
―それから、『ソフトマシーン』からは少し離れますが、あなたのテクノロジーについての興味というか、興味を越えたオブセッションというのも、これまでの作品では感じています。
カファイ:『未来身体へのプロスペクタス』プロジェクトのことですか?
―フェスティバル・トーキョーとKYOTO EXPERIMENTで上演された『Notion: Dance Fiction(ノーション:ダンス・フィクション)』のことをまずは思い浮かべていたんですが、あれはある意味典型で、テクノロジーを使いながらも反テクノロジーが同時にありました。歴史的に重要なダンサーの映像からその動きをデータ化してコンピュータに蓄積し、今度は生身のダンサーに筋肉をコントロールするセンサーというのかパッドのようなものを装着させ、歴史的なダンスをコンピュータのデータにしたがって再現する。もちろん、そんなことはいくらテクノロジーが進んでいる現在でもまだできなくて、フェイクだったわけですが。まあ、私はかなり騙されましたけど(笑)
『ソフトマシーン』でも、もちろんマニプルにカメラを持ち込み、スリジットの後をついて回るわけなので、少なくとも手段としてはデジタル・テクノロジーが重要ではあるけれども、だからといってテクノロジーの達成をひけらかすようなことはない。
カファイ:『ソフトマシーン』プロジェクトはいま取り組んでいる3部作の真ん中に当たるものです。『ノーション』が最初ですが、まず取り組んだのは身体コントロールの機能を脳から奪うことでした。先ほど説明してくれたように、デジタルの形式でコンピュータだけで振付けをするということですね。あの作品をつくっているとき、実は、振付家であれダンサーであれ、いったい何を考えているのか、ということに興味が湧いた。それで、これまでお話ししてきたようにさまざまな理由もあってリサーチで多くのアーティストに会ったのですが、そのプロセスで、3つめの部分に当たる作品をベルリンで初演します。『事物の振付』というタイトルにしましたが、そこでは、神経科学について私がリサーチしてきたこととダンスが一緒になるはずです。
自分でいろいろ実験するようになって、テクノロジーを使ったマルチメディアには限界があると思うようになりました。単にデジタルな表層として、背景にあるとかプロジェクションするとかインターアクションがあるとか、そういうことにどんどん興味を失っていきました。というのは、日本のスタッフと仕事をするようになって、デジタルなテクノロジーを使ったインターアクションでは、どうやっても日本人にはかなわないと思ったからです。それで身体へと焦点を移動していきました。
インベイシブ(侵襲性)・テクノロジーについて調べるようになって、マスター・センサーがデータを集め、それを電子化する。それがいま脳波で可能になっている。侵襲性といっても、私がやっているのは、攻撃的なことではなく、脳波センサーをダンサーに装着してもらい、何か質問したり、あるいは振付的なタスクを与えると、そのダンサーが何を考えているのか、脳波のデータを解読、解析すればわかるんです。本当のことを言っているのか、嘘をついているのか。私の指示に従っているのか、そうじゃないのか。私がやったのは、ダンサーの脳波から情報を収集することですが、ダンスを見ている側にも当然、何らかの刺激がある。そこにも関わっていけないかと。
―確かに科学的ではあるけれども、ユートピアン、あるいはその逆にディストピアンでもある。嘘発見器的なことは可能でも、それ以上のこと、情動の部分にまで介入していけるのでしょうか。
カファイ:もともとの発想は、振付家が作品について文章で書くことと、観客として見ていることとの間に溝があるということでした。もし脳波を使ってその人が何をやっているのか理解し、解読できればと考えました。
―そうしたデータについては、膨大に蓄積された神経科学系のデータや論文があります。専門用語で書かれていて難しいでしょうが。ただ、「ダンスをしているときに何を考えているのか理解する」というのは、口にするのは簡単ですが、実際可能なんですか?情動はどう分析するのでしょう?
カファイ:そういう意味では、可能じゃないですよ(笑)。そういう研究から明らかになったのは、脳はあまりに複雑で、トップの神経科学者であっても、簡単には答えられない。ある仮説を立て、脳のどの部分が活動し、どの部分が活動していないか実験してみる。ですから、ダンサーが何を考えているのかを解読するというのは私自身の仮説であって、私自身が観察し、私自身の方法に基づいて読み解くことしかできないです。
―そう言い切ると、根拠がないということになりませんか?
カファイ:実際、神経科学の専門家数人とすでに会って話していますが、私のやりたいことは理解できると言ってくれています。彼らにとっても、こういうリサーチは重要です。というのも、近年神経科学の研究は消費行動に関わるものばかりになっているからです。もちろん、消費行動の研究と重なる部分もありますが、私は別に問題提起をしようとか何かの商品を売ろうとしているわけではないですから。ただ、理解したいと思っているだけです。

―実際のパフォーマンスはどういう感じになりますか?
カファイ:ベルリンでやるのはギャラリー版です。4人のダンサーとそれぞれやって、一人40分の独自の作品というものを考えています。脳波をライブでストリーミングし、私がそれにコメントをしていく。もちろん、振付も私が考えたものです。
―コメントをする、振付を考えるとのことですが、具体的にはどのように?
カファイ:私のプロジェクトはだいたい2年くらいをサイクルに考えています。ベルリンでやる最初のシリーズは、『内省』と呼んでいて、彼が踊っているときに何を感じているかを脳波から理解する。ギャラリー版の次は、パフォーマンス版を考えています。最初のシリーズにはダンサーがいて、共同作業で振付的なスコアをつくりました。例えば、「じゃあ、ここで君の好きな音楽を使って踊ったらどうなるか、君が好きなテクストを読んだらどうなるか」といったことを試みます。そうやっていろいろ収集したり比較したりします。データを集めないといけない。
繰り返していくうちに、データを比べ、別の人に同じ身ぶりをしてもらって比べる、あるいは違うことをやってもらう。もし即興でやると脳波的にはどうなるのか。脳波のデータから記憶にアクセスしているとか、まったくアクセスしていないから、まったく新しい身ぶりで、ただ自分のエネルギーと流れに身を任せているだけだ、とか。
こういうふうに説明すると、専門的な研究に大きく依存しているようにも聞こえるかもしれませんが、できるだけ簡素にかつ文脈化するように心がけています。まるで科学の報告書のようにはなってほしくない。それでは私だって何を言っているのかわからない。観客に科学がアクセス可能であるようにしたいのです。 継続的に上演可能な作品にするにあたっては、どのダンサーでも使えるようにシステムを構築しようとしています。ある空間に行って新しいダンサーとも作業をして、そこで新しい「読み」ができる。もちろん、ダンサーにシステムに慣れてもらう時間やソフトウェアの同期が必要で、そうやって機械と相互理解してもらわなければなりません。コンピュータもまた知的存在だと私は考えています。ああしてくれ、こうしてくれ、と伝えるだけでなく、逆にこちらもコンピュータから指示をもらう。「条件付け」の期間を通過すれば、ともに作業することができるようになります。
―その結果どうなりますか?
カファイ:やってみなければわかりませんね。(笑)
作品創造の環境
―あなたは文字通りグローバルにプロジェクトを展開していますが、実験的な新しいアイディアは、ロンドンやベルリンといったヨーロッパのほうが理解があるという感触があるんですが、どうでしょうか?
カファイ:お金はアジアですね。(笑)
―おお、お金はアジアなんだ(笑)
カファイ:私の国籍がシンガポールということで、とても幸運なことに、シンガポール・アーツ・カウンシルから支援が受けられます。カウンシルが、作品創作の基盤になるリサーチへの最初の支援をしてくれるので、大変ありがたいと思っています。
ただ、シンガポールでは最近、作品はつくっていません。10年近くシンガポールでやっていたのですが、いつも結局、同じ人とやることになってしまう。シンガポールを離れて5年以上になりますが、その結果、創作の考えが明確になったり、自由な環境でつくることができるようになった。 戦略的にいうなら、アイディアの初期段階の助成は、アーツカウンシルや同じシンガポールのエスプラネード劇場のコミッションによるものが多くなっています。それで、ワーク・イン・プログレスの段階になると、ヨーロッパやアジアのフェスティバルなどから助成をもらっています。
―今はベルリンが拠点ですよね?
カファイ:ベターニヤン芸術センターに1年間のレジデンシーをしています。これも、シンガポールのアーツカウンシルの助成によるものです。
―ベターニヤンですか?伝説的なアートセンターですよね。ヤン・ファーブルが若いときにいたとか、日本の太田省吾さんが作品制作をやったとか。
カファイ:そうでしたね。今はどちらかというと視覚芸術中心ですが、選んでもらったのは光栄です。その前はロンドンに5年いて、ロイヤル・コレッジ・オブ・アートでデザインの勉強をしていました。そこでは「思索的デザイン(Speculative Design)」というものを専攻しました。

―「思索的デザイン」とはなじみのない分野ですが、どういうものですか?
カファイ:批評的デザインということです。何らかのサービスのため、製品をつくるためのデザインではなく、社会批評あるいはコンセプトや思想を批評するためのものです。思索的デザインとは、可能な未来に向けてある状況、ある解決策をデザインするという趣旨です。 3部作の最初の作品を作ったのも、私がこの大学での経験から、ダンスのテクノロジーの未来とは何かということを考えたからです。ダンスを記録する、ドキュメントするというそれ以降の創作も、その流れにあります。
―それはまた、アーカイブという、近年研究者からはじまって実践家の間でひどくはやっている概念というか、実践の理念とも関係しますね。なぜ最近アーカイブがアーティストにとって重要になったのでしょうか?
カファイ:ここ5年くらいでしょうね。理由はよくわかりませんが、何となくアーカイブという問題を考える必要があるという認識がアーティスト間に広がった感じがある。
―それまでの図書館が映像資料を収集するというアーカイブとはちがう?
カファイ:ニューヨーク公立図書館の舞台芸術分館が、ダンスの映像アーカイブをインターネットでアクセスできるようにしたのも、ようやく昨年のことです。ただ、『ソフトマシーン』はそういう意味でのアーカイブとは異なります。もちろん、そこにはダンスについての歴史的問題が入ってきますが、私は今、何が起きているかに興味があります。ですから、同時進行の生きたアーカイブであって、過去からのアーカイブではない。
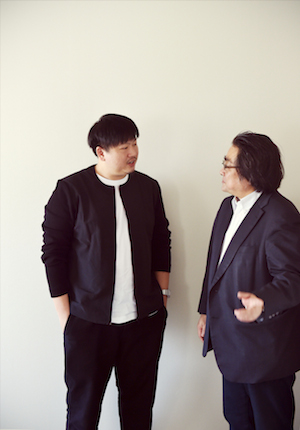
「非重要の歴史」への興味と作品への応用
―ところで、これまで『ソフトマシーン』と脳波を分析する作品について話していただきましたが、その他に、今抱えているプロジェクトというのはありますか?
カファイ:『非重要な歴史(insignificant history)』というプロジェクトもあります。シンガポールを拠点にしていたときに始まったのですが、最初は第二次世界大戦中にシンガポールにつくられた日本の神社についてのものです。今や廃墟になっていて、歴史の教科書にも出てこない。誰もその話をしない。こういう、忘れられた、「非重要」と私が呼んでいる歴史に興味があります。それは今日的にはどういうもので、私たちの世代にとって何を意味するのか、それを理解することに興味があるんです。 2012年だと思いますが、シンガポール芸術祭で発表したのもあります。これは、インドネシアにあった客家中国人の共和国についてのものです。その107年の歴史とシンガポールの50年の歴史にはかなりの共通項があって、一種の平行世界のような感じになっている。こういう「非重要な歴史」が、私の作品のもう一つの流れを作っていて、展示やパフォーマンス作品となることもあります。
―「非重要」というのがいいですね。もちろん、一方で公式な歴史というのがあるわけですが、公式の国家の歴史に対して、人民とか民衆の歴史というのはいつだって対抗的に立てられます。ですが、そのどちらでもない「非重要」というのがおもしろい。
先日シンガポールに行ったのですが、あなたが学んだラサール芸術大学の創立30周年記念の展示を見てきました。そこに出品していましたよね?
カファイ:そうです。一部ですが、2009年に始めたプロジェクトを出品しました。1777年、インドネシアのポンティナクに客家中国人の国ができました。金の採掘に中国人が大勢押しかけていたのですが、ビジネスとして強大になり、土地に主権をもつようになり、共和国になった。選挙で指導者を選んだからです。そのため、学者たちはそれを「東南アジアでの最初の共和国」と呼ぶようになりました。アメリカ合衆国憲法ができる10年前です。そこが興味の出発点でした。ポンティアナクから30分くらいのマンドールにある、かつて共和国の首都があった場所に出かけていって、客家中国人の末裔とか共和国の名残を探しました。共和国は公式には1884年になくなってしまったので、相当時間がたってしまっています。でもまだ名残があり、共和国の創始者を崇拝する人々がまだいます。インドネシア人と混血の客家中国系人もいて、その創始者の生まれた町に行きました。その末裔がまだ住んでいてインタビューしました。この共和国についての資料は、実はすべてオランダのライデン大学のアーカイブにあるので、そこにも行きました。
―ああ、オランダの大学ですか。元宗主国、ですものね。
カファイ:調査の結果、107年間、確実にその共和国が存在していたことがわかりました。シンガポールの歴史と似ているんですよ。最初はビジネスで人が集まり、力を得るようになると、中国から孔子学者を呼んできて子どもたちの教育をさせる。1980年代のシンガポールで起きたことと、まるで一緒です。産業的というか企業的な意味合いを重んじて整備された罰則があることも同じです。あまりに似ているので、シンガポールの歴史について考えるために、この共和国の歴史について考える必要があると思いました。
―これは現在も継続中のプロジェクトですか?
カファイ:一応、2012年で終了しています。ただそれは、素材がすべて揃ったというだけで、もっと一般観客にアクセスしやすいかたちで、構成を変えて何かしようと考えています。
―今日はいろいろと興味深いお話をありがとうございました。今後のプロジェクトも楽しみにしています。
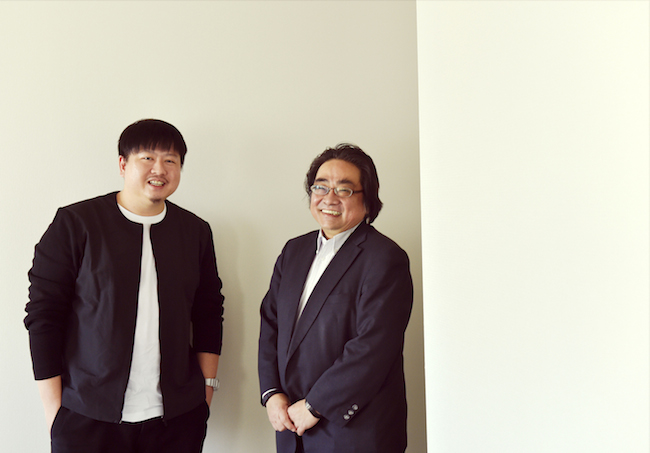
【2015年2月12日、横浜市桜木町にて】
聞き手: 内野 儀(うちの・ただし)
1957年京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了(米文学)。学術博士(2001)。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は日米現代演劇、パフォーマンス研究。著書に『メロドラマの逆襲』(勁草書房、1996年)、『メロドラマからパフォーマンスへ』(東京大学出版会、2001年)、“Crucible Bodies” (Seagull Press、 2009)等。セゾン文化財団評議員、神奈川芸術文化財団理事、アーツカウンシル東京ボード委員、ZUNI Icosahedron Artistic Advisory Committee委員。表象文化論学会理事。






