マレーシアでの上演、そして「マレー的」なるものの問題
―あなたとマレーシアとの関係は非常に深く、長いものですね。私が最初に見たあなたの作品は、シンガポールのテアター・エカマトラ、クアラルンプールのアクターズ・スタジオによる『コーズウェイ』という作品でした。2002年のことです。マレー語で書かれた短い作品のオムニバスでした。

アルフィアン:ちょっと頭の中を巻き戻してみないと……。『コーズウェイ』は参加アーティスト全員による共同作業で作った作品でした。その過程で私が気づいたのは、お互いの国についてのイメージの釣り合いがとれていないということでした。私たち、テアター・エカマトラの側のメンバーはクアラルンプール出身の俳優たちと仕事をすることになったわけですが、そのうちの何人かはシンガポールに行ったこともありませんでした。彼らにとっては、シンガポールは買い物天国というイメージしかなかったのです。シンガポールと2つの橋で直接つながっている南部のジョホール州の俳優とのワークショップだったら、だいぶ違ったことになったでしょう。もしペナンの出身者がいたら、また違ったものが見えてきたかもしれません。ペナンも島ですし、かつてはマラッカ、シンガポールと並んで英国の海峡植民地だったわけですから。しかし、このような非対称的な状況というのはなかなかおもしろいものでした。シンガポール人、特にマレー系シンガポール人はマレーのポピュラーカルチャーの多くはマレーシアからやってくるという感覚を持っていたのですが、それが逆になることはなかったのです。
―その後も、あなたはマレーシアのアーティストとの仕事を続けています。マレーシアのインスタントカフェ・シアター・カンパニー(ICT)が2012年にクアラルンプールで上演した『ナディラ』は特筆すべき成果を上げたと思います。シンガポールでの上演のために用意されたオリジナルバージョンからは、少し手直しをしたと聞いているのですが。

Nadirah (c)Teater Ekamatra
アルフィアン:そのとおりです。登場人物のひとりに、非常に元気がよく、独立心も旺盛なマレー人の少女がいます。彼女は主人公の親友で、ふたりともシンガポール国立大学に通っています。この登場人物をマレーシア人にしたのです。他の台詞にはほとんど手を入れませんでしたが、彼女だけをマレーシアからの留学生という設定にしました。これによって、マレーシアにおける民族問題に触れてみたいと考えたのです。また、シンガポールのマレー系の少女なら持ち得ない心の傷を彼女に持たせたいとも考えました。例えば、若いムスリムの女性に対してトゥドン(スカーフ)をかぶれという圧力は、マレーシアの大学でのほうがはるかに大きいでしょう。マレーシアの大学のキャンパスではイスラム教徒のマレー人が多数派であり、だからこそ彼女の行動や服装への監視は強いはずだからです。
―このような変更は、マレーシアの観客が自分のことと感じられるような要素を増やすため、ということなのでしょうか。
アルフィアン:そうです。海外に作品を持って行くときには、その国の観客が作品に自分を重ねることができるようにするための何らかの橋渡しをしてあげることが有効だと常々考えています。修正のもうひとつの理由は、演じたのがマレーシア人の俳優だったということです。私にとって、俳優が自分の役に没入できるようにすることはとても重要なのです。なにも、マレーシアとシンガポールがまったく違うと言いたいわけではありません。

Parah (c)Teater Ekamatra
―ご自分の作品、特にマレー語の作品をマレーシアで上演するというのはどんな気分なのですか?
アルフィアン:これまでに数本のマレー語の作品をマレーシアに持っていきました。2000年代の初めにやったのは2本立てで、そのうちの1本は『マドゥ・ドゥア』というタイトルでした。「マドゥ」とはマレー語で「蜂蜜」の意味です。でも、この言葉にはイスラム教徒には許されている、第2、第3夫人との結婚という意味もあるのです。この作品はそのような一夫多妻制を扱ったもので、伝説的なマレーの映画スター、P. ラムリーの『マドゥ・ティガ』という作品のパロディでもあります。このタイトルは「3つの蜂蜜」という意味ですが、劇中のP. ラムリーには3人の妻がいます。ただ、彼女たちはお互いに知り合うことはありません。私の『マドゥ・ドゥア』は、夫の帰りを待ちわびるふたりの女性を描いた作品です。女性の視点から物語る、フェミニスト的な戯曲でした。
それから『アナ・ブラン・ディ・カンポン・ワハッサン』―これは「ワハッサン村の新月」という意味ですが——という作品も上演しました。近代化の犠牲となって消えていこうとするシンガポール最後のマレー・カンポン(村)を描いたこの一人芝居は、まずクアラルンプールで上演され、後に西マレーシア各地の6つの地方都市で巡回上演されました。
私は、常に自分のマレー語の作品をマレーシアに持っていきたいと思ってきました。新しい観客を発掘するということだけではありません。マレー語はマレーシアの国語ですから、これらの戯曲はマレーシアでは民族を超えて受け入れられるのではないかと思ったのです。実際、マレーシアでは、多くの非マレー系の観客が劇場に足を運んでくれました。多様なバックグラウンドの観客に見てもらうということはとても興味深い経験です。もちろん、シンガポールでも多様な観客が来てくれるのですが、それは英語字幕のおかげにすぎないのです。
―シンガポールとマレーシアの近さ——地理的な近さだけではなく、社会的・政治的な事情を含めて——は、この2つの国の間のコラボレーションを独特で興味深いものにしています。でも、一方では難しさもあるのではないかと思うのですが。
アルフィアン:『ナディラ』を上演した劇団、ICTはもうひとつ、『パラ』という私のマレー語作品を上演しています。

Parah (c)Instant Cafe Theatre Company
これは2011年頃に大きな議論を巻き起こした「インターロック論争」と呼ばれる事件をベースにしたものです。作家のアブドゥラ・フセインが1960年代半ばに書いた『インターロック』という小説を、マレーシア政府がマレー文学の教科書として採用したことが論争の発端でした。この小説では、マレーシアのインド人を「パリア」という下位のカーストに属する者と位置づけているのですが、これはインド人コミュニティにとっては非常に屈辱的な扱いだと見なされたのです。このような問題がある本が学校で使われ、あらゆる民族の生徒たちがそれを読むことになるということに対して、NGOや社会運動家は公に疑問の声を上げました。
この問題は、単にマイノリティへの配慮ということにとどまりません。この論争は、マレーシアにおける多文化主義の政治性について根本的な疑問を突きつけ、社会における民族・文化問題がいかに複雑であるかを見せつけたのです。このような題材を扱う作品をマレーシアに持って行くにあたっては、「ほら、マレーシアの問題をよそ者のシンガポール人が書いてるよ。なんで外国人に私たちの話をしてもらわなくちゃならないんだ?」というような反応があり得ることをよく承知していなくてはなりません。でも、こんな反応は欲しくなかった。私が言いたかったのは、「でも、私たちにはたいした違いはないんです。本当に、本当にです。私はどこか遠い国から突然やってきて、あなたたちの社会がどんなかを理解しようとしているわけではないんです」ということです。私はマレーシア人ではありませんが、でも彼らの社会について、ある種のインサイダーとして書くくらいには知っているのです。実際、私が『パラ』を書くにあたって参照したインターロック論争についてのニュースやコメントは、すべて私のFacebookに投稿されたものでした。


―マレー系はシンガポールではマイノリティですが、マレーシアでは多数派です。それは影響しますか?
アルフィアン:答えるのは難しいですね。もちろん、マレー語はマレーシアでは支配的です。それは認めますし、それに自覚的でなくてはいけないとも思います。常に自らを省みることも必要です。私がマレーシアでこのような支配的な言語を使う時、それは別の種類の支配を生み出してしまうことにつながるのだろうか、と。同時に私の芝居は支配的なものへの反論でもあります。マレーシアで高いステータスを得ている戯曲の多くは文学的な言葉で書かれているのに対し、私の戯曲のほとんどは普通に市井で使われる日常語で書かれているからです。
人々が「おい、このマレー人作家はシンガポールの奴だぜ。マレー語と英語をごちゃ混ぜにしちゃってるよ」と言うかもしれないということは自覚しています。ただ、私が強調したいのは、これこそがシンガポールで話されているマレー語なのだということです。マレー語演劇の世界では、演劇は文学の延長なのかという論争がいまだに残っているように感じます。マレーシアでは、国民文学賞などに代表される、官製の文学が存在しています。その文脈では、言語の純粋性が突如重要視され、英語の単語が入ってきたりすることを極度に恐れるのです。
―シンガポールにおける言語による演劇の分断に触れておられましたが、マレーシアではそれがいっそう顕著なのではありませんか?ICTは英語劇団と認識されていると思いますが。
アルフィアン:そうですね。でも、ICTも進化を続けていると思います。彼らの初期の定番は、時事問題を扱った政治風刺劇やパロディでした。これは中産階級のリベラル層や在留外国人などに人気でした。でも、劇団のディレクターであるジョー・クカサスが様々なバックグラウンドを持つアーティストたち、例えばシンガーソングライター・劇作家・社会活動家など様々な顔を持つアーティストであるショノン・シャー、他の言語で演劇活動を行っていたナム・ロンやロー・コクマンなどと作品を作るようになって以降は、ICTの観客にも変化が見られます。それまでとは異なる、さらに広範な人々の関心をひくようになったのです。このような混交性こそが、私がICTと仕事をするようになった理由です。『ナディラ』上演にあたり、いわゆるマレー語劇団ではなくICTをパートナーに選んだのもそのためです。
現在のカテゴリー分けにとらわれないことが重要です。クアラルンプールのマレー語演劇の中心である国立言語局のストー・シアターで、マレー系だけを相手に作品を上演したくはないのです。ですから、ICTと一緒にやることには意味がありましたし、実際、より多様な観客に私の作品を見てもらうことができたと思っています。

インターカルチュラル・コラボレーションとプラットフォーム
―国境を越えたインターカルチュラル・コラボレーションのための土台はかなりできあがっているようですね。
アルフィアン:ええ、コラボレーションの機会は拡大しています。エキサイティングなことです。私は東南アジアのアーティストたちのネットワークにはうまく収まっていないのだろうと思うのですが、それでもTPAMのようなプラットフォームは非常に有効だと思いました。オフィシャルなグループ・ミーティングやインタビューで色々な人に会うことができるのに加え、夜に気楽な感じでバーで話をすることもできる。これまでも折に触れて地域のアーティストと出会うことはありましたし、横浜で会ったアーティストの中にはすでに知っている人たちもいたのですが、集まって互いに話すことができる継続的な基盤があることで、また違った種類の出会いが生まれるのではないかと感じました。
横浜ではゆったりした気分で、これまで話したことがなかったことを話すことができました。ある晩には、東南アジアとは何かがテーマでした。スリランカが東南アジアの一部であってはなぜいけないのか?なぜミャンマーは東南アジアの一部であって南アジアの一部ではないのか?ベトナムは北東アジアの一部ではないのか?こんなに中国的、儒教的な文化の影響が色濃いじゃないか。誰がこんな風に決めたんだ?CIAか?共通項ってなんだ?
このようなTPAMでの経験を通して考えたことがあります。ダンス分野での交流はたくさんある。それはすばらしいことですが、少し易きに流れているところはないのでしょうか。というのは、ダンスではこの地域における言語の問題を回避することができるからです。もし、東南アジア各国のアーティストがひとつのプロジェクトを共同で実施するとき、コミュニケーションのための共通言語は何が適当なのでしょうか。英語がデフォルトになるのでしょうか。ASEANの会合ではインドネシア語を使おうという提案がされたと聞いたことがあります。その言語を話している人口ということで言えば、この地域で最大の言語だからです。しかし、人口だけが決定要因なのでしょうか?この問題はきちんと考えなくてはいけないと思っています。
―日本のアーティストについてはどうですか?
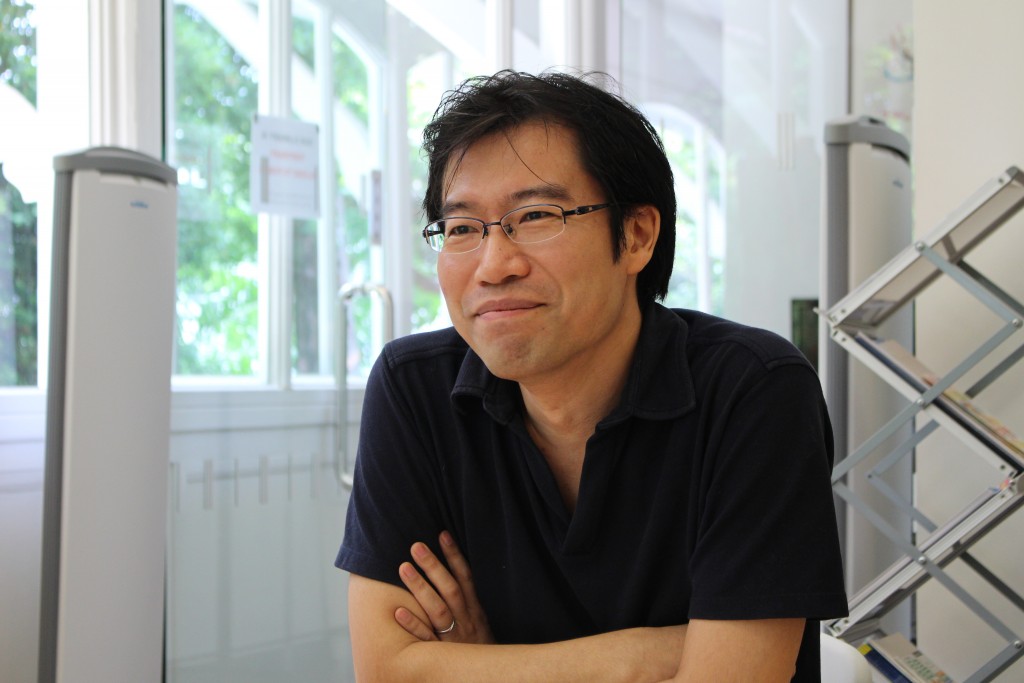
アルフィアン:滞在中、若いアーティストの作品をいくつか見る機会がありました。なかでも濵中企画さんの『かげろう ―通訳演劇のための試論―』というドキュメンタリー作品に強い印象を受けました。2011年の津波で夫を亡くした福島の女性の声がフィーチャーされます。私はその女性のインタビューを聞いているわけですが、同時通訳も行われています。きわめて感情を抑えた通訳で、通訳者はその女性が語ることを演じてしまわないように細心の注意を払っていました。それが作品を非常に感動的なものにしていたのです。
興味深かったのは、この作品には常に何らかのギャップが存在し続けていたことでした。日本語と英語の翻訳のあいだにあるギャップ、悲劇の実体験と舞台上での表象とのあいだのギャップ。翻訳のプロセスで失われたのは何だったのでしょうか?とてもシンプルな作品でしたが、本当に感動しました。のぞき趣味に堕することを避けるための、敬意ある距離の取り方とでも言うべきものがありました。これは本当に気に入りました。
―日本に関連するテーマについて書くことに興味はありますか?
アルフィアン:実は、現在、日本占領期のシンガポールについてのリサーチを進めているのです。特に篠崎護という、日本軍政下の官僚についていろいろ調べています。彼は「日本のシンドラー」とも呼ばれ、抗日活動に関わっていないという証明書を多数発行しました。交付を受けた人々は、それによって日本軍の憲兵隊の目を逃れることができたのです。
シンガポール国立公文書館で占領期に関するインタビューや記録を調べていたとき、多くの人たちが彼について話しているのを見つけました。しかし、同時に気づいたのは、この日本人にどのように命を救われたかについておおっぴらに語ることへの恐怖感が存在することでした。人々はそれを避けているかのようでした。それは生き残ったことへの罪の意識―「多くの人たちが殺されたのに、私を救ってくれた人のことなど話したくない」というような―なのでしょうか?それとも、「彼が私の命を救ってくれたのは、私が日本軍に協力していたからだと思われるんじゃないか。そうしたら困ったことになるのでは?」という恐れなのでしょうか。篠崎はシンガポールでは賞賛を受けてはいません。おそらく日本でもそうでしょう。このような人間の基本的な優しさから出た行為が、当時の政治に絡め取られてしまったということなのでしょうか。今日においてさえ、戦争の罪に関するポリティクスがこのような種類の恐怖心を生んでいるのでしょうか。これを探ってみたいと思っています。
―日本とシンガポールの歴史には、掘り起こすべきものがまだまだたくさんあります。同時に、演劇がそうした問題に取り組もうとしたときには常に緊張関係が生まれてきました。このプロジェクトであなたが歴史の複雑さにどう取り組むのか、とても楽しみにしています。

【2016年2月22日、シンガポール ジャパン・クリエイティブ・センターにて】
聞き手:滝口 健(たきぐち・けん)
シンガポール国立大学英語英文学科演劇学専攻リサーチフェロー。専門は東アジア・東南アジア地域における演劇翻訳、インターカルチュラル・シアター、文化政策。国際交流基金クアラルンプール事務所勤務時代以来、ドラマトゥルク、翻訳者、プロデューサーとしても活動し、多数の国際共同制作作品に参加。ワイルド・ライス作品『ホテル』には日本語翻訳で参加。






