ダンスは元来、外で踊るもので、劇場で行われるようになったのは近代以降なんです。(石井)
石井:ニューヨークのブロンクスの路上で生まれ、世界へ広まったストリートダンスですが、歴史を振り返ってみても、ダンスは元来、外で踊るもので、劇場で行われるようになったのは近代以降なんです。古代・中世に儀式や祭祀としてはじまり、やがてクラシックバレエに象徴されるように、近代社会のヒエラルキーのなかで「劇場というシステム」に取り込まれたわけですが、いま再びそこから解放されようとしている。ストリートダンスも、権威や財力を必要としない、身体ひとつで表現できる若者文化として、エネルギーを爆発させてきたんですね。
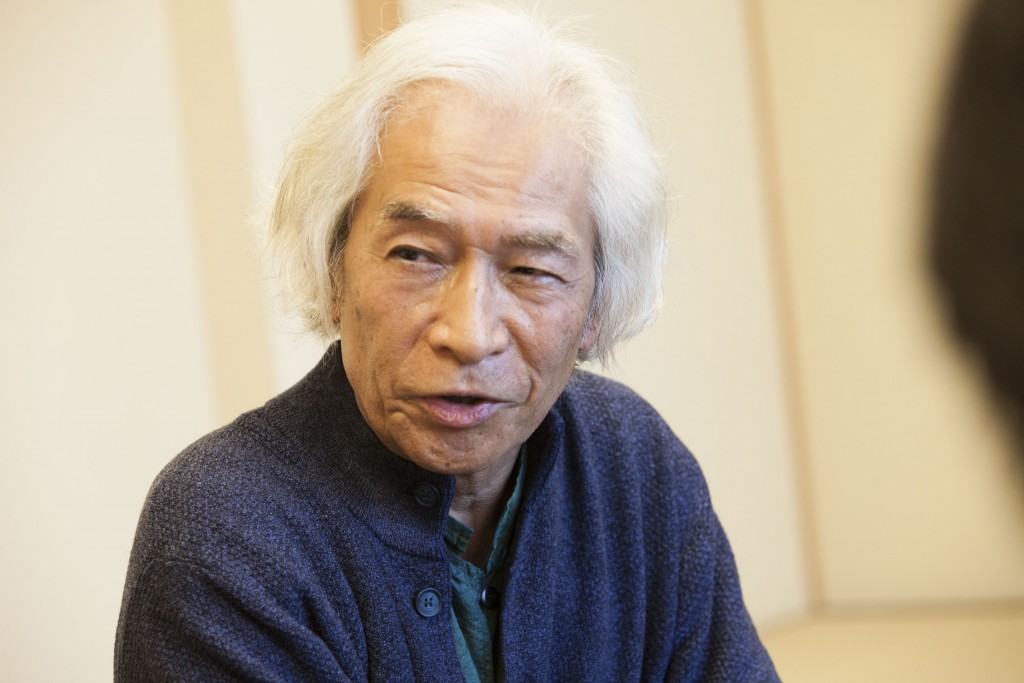
shoji:高校生のころ、海外のミュージックビデオに出てくるかっこいいダンサーたちに憧れを抱きました。大学でダンスサークルに入ってダンスをはじめ、夜中に公園やビルの前で練習しましたが、当時は不良がたむろしていると思われて警察に通報されたり、肩身の狭い思いをしていましたね(苦笑)。安室奈美恵さんやEXILEの登場で、社会的にも一気に認知が広がり、いまでは親が子どもにダンスを覚えさせて、芸能界デビューの夢を託すことすら珍しくない時代になっているんですよ(笑)。
石井:ダンスを「時間」と「空間」の表現と考えるなら、プレゼンテーションの場は無限で、東京のような過密都市でこそ開拓の余地がありそうですね。廃屋や廃校もいたるところにありますし。「DANCE DANCE ASIA―Crossing the Movements」でびっくりしたのがフィリピンのチームPHILIPPINE ALLSTARS。フィジカルな能力がすごいだけでなく、民族性や風土に根付いた、自分たちの足もとから生まれる作品を作っていました。まさにストリートの闇、ガード下の情景を反映したダンスですね。

「DANCE DANCE ASIA―Crossing the Movements」 東京公演 PHILIPPINE ALLSTARS
©Tadamasa Iguchi / DANCE DANCE ASIA
shoji:歴史の関係からか、フィリピン人はラテン気質というか、情熱的で開放的なのに、アジア的な人間の温かみがある表現は、日本人が持っていないものですよね。マニラで行なった「DANCE DANCE ASIA」のワークショップもすごく盛り上がり、これからもっとおもしろくなると思いました。彼らのダンスは「心」で踊っていることが伝わってきます。アメリカでもいまシーンを引っぱっているダンサーにはじつはフィリピン系が多いんですよ。アジアのダンス文化には、日本では生まれてこない独自のものがある。日本勢はうかうかしていられません。

「DANCE DANCE ASIA―Crossing the Movements」マニラ公演 ワークショップの様子
©Vincent Coscolluela / DANCE DANCE ASIA
石井:フィールドワークの経験からいえば、韓国、インドネシア、インドには土地に根付いた独自の伝統的な舞踊文化があり、それぞれがあまりに豊かで、時に刺激的で圧倒されます。それは祭儀としての枠組みを踏襲しながらも、体の芯からパワーを放出する「魂」のある身体文化なんです。日本の舞踊文化は、型や技芸の鍛錬には長けていて、それを美として完成させるのだけれど、その奥にあるべき「魂」が欠落してしまうのを見ることがあります。現代のパフォーマンスは、既存のものからどれだけオリジナリティーを生み出せるかが問われる時代。自分自身を育んだ文化とは異質な身体言語に積極的に触れることで、違う次元の作品が生まれてくる。観客もダンサーも領域を超えて交流し、自分をひらいていくべきですね。
単に「ダンス」って呼んでいいと思うんですよね。先輩たちへの敬意をこめるなら、安易にストリートとは呼べませんから。(shoji)
―日本のストリートダンサーを見ていると、ある特定のスタイルを一途に追究したり、縦社会的なイメージを感じることもあるのですが、実際はどうなんでしょうか?
shoji:多くのダンサーは、新しいスタイルにチャレンジすることに抵抗感はないように思いますが、シーンがいまのように大きくなかったころから、日本でストリートダンス文化を手塩にかけて育ててきたオリジネイターの方たちには当然誇りもありますし、「それはちがう」「ヒップホップじゃない」というこだわりを持つダンサーももちろんいます。石井さんのおっしゃられるとおり、日本人が伝統や様式美を大切にするのはストリートダンスでも同じで、欧米では人口が減ってしまった歴史のあるスタイルが日本では進化を続けていて、それを学びにくる外国人ダンサーもたくさんいるんです。
―それはすごい(笑)。
shoji:1つのスタイルを追究し続けるダンサーもかっこいいと思いますし、一方、コンテンポラリーダンサーと一緒にクラブでパフォーマンスをしたり、ジャズやバレエを取り入れたワークショップやレッスンを行なうストリートダンサーもいて、そちらも非常に魅力的に感じます。ぼく自身もハイブリッドに抵抗感はありません。音楽も多くは既存の曲を使いますが、最近はジャンルも色々ですし、ここ数年は自分もヒップホップで踊っていないんです(笑)。だから、単に「ダンス」って呼んでもいいと思うんですよね。おおざっぱなジャンル分けのほうがラクでいい。先輩たちへの敬意をこめるなら、僕らのダンスを安易にストリートダンスとは呼べませんから。

石井:ダンスにとってサウンドは重要で、時にはダンサーの身体以上に物語ることがあります。既成の音楽に限界を感じて独自に編集した音源や、音を使わず無音の空間で身体性を際立たせるような作品もある。アメリカのポストモダンダンスやコンテンポラリーダンスは「既成概念」を乗り越えることで発展してきたので、特にどんな音や音楽を使うのか、使わないのかということに、ダンサーはセンシティブでなければならない。たとえばフランスで出版されたコンテンポラリーダンスの本で「ノンダンス」という言葉がタイトルの一部になっているものがあります。まさに「踊らない」ダンス。作品として時間と空間を満たす必然性がそこにあれば、ダンサーがそこにいること自体がアートになりえます。
shoji:ノンダンスは偶然、映像で見たことがあります。パフォーマンスがはじまっても全然動かないから、コーヒーを入れて戻ってきたら、まだ同じ位置に立っていた(笑)。途中で出て行く観客もいたり、ついつい早送りしてしまいましたが、ダンス文化を挑戦的に切り拓いてきた歴史の一部だったんですね。
石井:もちろんテクニックの魅力はあらゆる種類のダンスにあって、訓練された身体性もとても重要です。ただ、バレエでもピルエット(回転)が得意だからといって回転ばかりしているダンサーがいないように(笑)、ダンスという表現はテクニックを競うのがすべてではなく、自分がいまいる空間をどう扱うのか? ということや、踊っている根底にどんなコンセプトがあるのか? ということなど、トータルの表現の可能性がひらかれています。それらをどういうバランスで観客に訴えるのかということですね。






