なぜ演劇を?
藤岡:どうやって演劇の道に進んだのですか? ご家族はその選択に同意しましたか?
ソウ・モウ:私がドラマや演劇が好きなのは、人間に近いからです。そして、ひとりで行う作業でないからです。孤独はいやですし、演劇なら多くの友人や同僚と一緒にできます。
藤岡:コミュニティみたいな存在?
ソウ・モウ:そうです。そして演劇やドラマを通して地域社会にメッセージを波及させることができると思います。
藤岡:ご両親は賛成?
ソウ・モウ:わけがわからないようです(笑)。「最近何している?」「劇に出てるんだよ」「えっ? 何それ」という会話ばかり。でも少なくとも教師である、ということはわかってもらえたみたい。
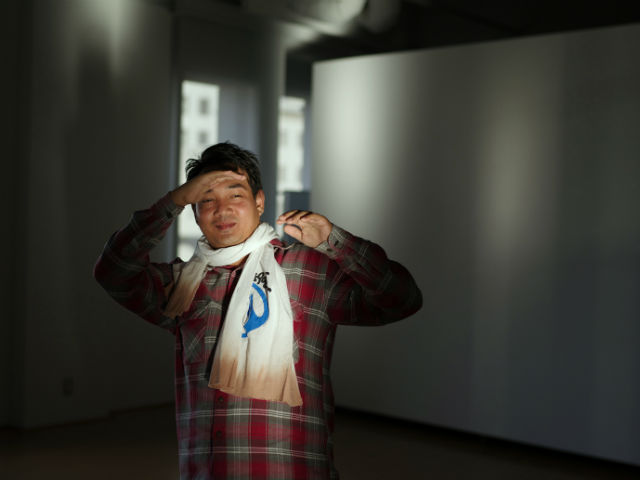
ティラ:私の母方の祖父はキン・マウン・ニュンという有名な俳優で、第二次大戦後のミャンマーで舞台と映画で活躍しました。日本にも来たことがあるそうで、訪日して彼自身の映画の編集をしたそうです。母からそう聞きました。しかし母の世代以降、芸術に携わる人はいませんでした。私は若い頃から芸術が大好きで、歌手になりたかったんです。でも牢から出されたあと、演劇を選びました。誰にも理解はされませんでしたが。当時、芸術に携わる人は人気を商売に結び付けることしか興味がありませんでした。「君はうまい俳優だから、映画をやれ。コマーシャルや映画がいい」と。でも私はそうはしませんでした。妻にも、結婚して2年たつまで理解してもらえませんでした。
2010年か2012年にようやく私たちの仕事の成果がわかってもらえるようになりました。今では社会的な評価は高まっています。妻も、この仕事が地域社会を助けることなのだとわかってくれるようになりました。でも母はまだ「なんでそんな、何の保障も給料もないような仕事をしているの?」と言います。3ヵ月も収入のない状況が続くと「オフィス勤めして安定した月給をもらったら?」と言われます。かつて政治囚でしたから、アメリカに渡航することは容易ですが、その道は選びませんでした。いくら母が「アメリカ留学して、新しい人生を切り開きなさい」と言っても、私は「母さん、ゴメン」と言いました。
私はミャンマーにとどまって地域社会の役に立ちたいと強く感じているんです。私の目から見ると、政府は変わっていません。かつて革命のさなかにいて、民主化運動の一員でしたので、状況はよく承知しています。
2010年よりも前、ボンド・ストリート・シアターと共同製作したプロジェクトがありました。ヤンゴン郊外の農村地帯に赴き公演をしました。警察が来て「ここでは禁止だ。ヤンゴンに帰れ」と言われたことがありました。それに対して「わかった、観光地とか別のところに移動するよ」と答え、一晩だけ離れて、次の朝にはほかの農村地帯で上演活動を続けました。リスクを背負って、やったのです。そういう仕事を私は続けたいと考えて、私はミャンマーに居残りました。当時、そのことを理解する人はいませんでした。現在は活動が注目され、政府も変わりつつあります。すっかり変わったとは言えませんが、少しずつです。

藤岡:ミャンマー国外にいると一夜にして民主化したと思いがちですが、変化の速度はそうではないのですね。
ティラ:周囲の人は私の仕事を理解し始めました。しかし古典演劇界からは未だ「プロでない」と言われます。私たちの演劇が屋外公演で無料だからです。法的に登録された劇団にならなければ、古典演劇の協会からは認めてもらえません。公演の度に地元当局に掛け合うとき、活動を阻もうとする嫌がらせで法的な登記簿を要求されることがあります。どうにかやっていますが、公式な登録はまだなのです。
ソウ・モウ:表現の自由にかかる制約は緩まっていますが、公演を実施するには未だ政府の許可が必要です。だから法的な地位が必要なのです。
民主主義とアート運動
藤岡:ミャンマーにおける民主主義運動と舞台芸術運動の関連について興味があるのですが。
ティラ:非常に強い結びつきです。私たちの公演で、観客は批評的な思考を求められます。これは民主化の重要な側面です。批評的な思考を育てる。だからこそ現代アートの運動は我が国の民主化にとって大事なのです。
エリートの知識人は既に批評的な思考を身につけていますが、一般庶民は日常生活をこなしていくだけで精一杯ですから、余裕がありません。私たちの演劇なら、親しみやすい方法で物事を問い返すことを身につけられる。自分で考えて判断する能力は彼らにあるのですから、考えろと言うんじゃなくて、自分で考える能力を回復する機会を提供するのです。
藤岡:サイクロン「ナルギス」の後、被災者の支援活動をやりましたね。舞台芸術や演劇はコミュニティの復興をどう助けることができるのでしょう? 日本では2011年に大きな地震がありました。アートが社会的な大惨事の被害者をどう支援できるのか、考えています。

ソウ・モウ:当時、地域社会の構成員全員を対象とした支援団体もありましたが、私たちは子どもに焦点をあてました。子どもたちがトラウマと折り合いをつけ、心理的に癒され、心身の健康を取り戻すことができるように、社会心理学的なサポート・プログラムを実施しました。9ヵ月の間、ほぼ毎日です。
ティラ:アーティストたちが地域を訪れ、とどまり、毎日村々を訪問してアート教室を開催しました。お遊戯の中に演劇を取り込んだり、演劇を上演したり、コメディアンたちとコラボレーションもしました。
ソウ・モウ:昔ながらのスタンダップ・コメディです。
ティラ:また、NGOからの依頼で公衆衛生の広報の手伝いをしました。デング熱や下痢、手洗いの奨励、下痢のときは水分補給をしましょう、とか。教育(エデュケーション)だけど楽しい(エンターテインメント)、というエデュ・テインメント活動です。そのプログラムのあとに、通常の演劇の舞台をやったりしました。
藤岡:ナルギス後の復興は?
ティラ:人々は心理的には治癒したと思います。しかし田んぼが海水で浸水してしまいましたので、もう稲作ができません。社会的な復興はまだ困難なようです。
技術サポートと批評的思考
ティラ:海外に期待したいことに、資金的援助がありますが、文化的なサポートも必要です。人材という面では技術スタッフが必要です。照明、音響、舞台美術など。ミャンマーでは不足しています。ひとりで俳優、舞台監督、衣装、メーク、すべてをやっているのが現状です。私は演出家ですが他のあらゆる業務も兼任しています。現在はそれでやりくりしていますが、長くはこの形では続けられないでしょう。技術部門の専門家が必要です。観客と市場さえ育てば、雇用先として若い人たちを呼び込むことはできるとは思うのですが。
芸術では食えない、と人は言います。でも実際、生計は立つのです。利益主義、商業主義を追求しないで、産業と市場を創出できれば、地域社会のための芸術を続けることができます。数年のうち、さらなる人材を育成するための資金を集めることができるでしょう。ある程度、資金というのは重要なんです。だから、投資家を歓迎します。芸術産業への投資をぜひご検討ください。
藤岡:ヤンゴンで、スマホの普及に驚きました。いま、世界の情報が一気になだれ込んでいますね。
ティラ:そうです。だからこそ、批評的思考が必要です。非常に重要なんです。それがなければ国の一大事です。軍事政権のもと、私たちの思考は死滅させられました。そういう意味で、闘いはまだ終わっていません。多くの情報が押し寄せ、取捨選択の管理がとても難しくなっています。だから特に若い人たちの間の批評的な思考を育て、実践する場が必要です。私の世代はどうでもいい、まもなく去る世代です。でも次の世代にとって肝心です。今のところ、若者たちはマネばかりして、耳目に入ったすべてを無条件に受け入れています。消費主義の輸入が進んでいて、それも大きな問題です。

藤岡:芸術を考えるとき、ミャンマー固有の価値観やアイデンティティは大事ですか?
ティラ:はい。ミャンマーのアイデンティティを守る必要はあると思います。人間誰しも、おのずの自己同一性がありますよね。私はグローバリゼーションや近代化に賛成ですが、地域に根差したアイデンティティというものも信じています。何を残し、何を手放すべきなのかはわかりませんが、ローカル・アイデンティティは非常に貴重だと確信します。例えば我が家では、母親が家族の人生に色濃く影響を及ぼしています。私の今の年齢でも、私生活に踏み込んできます。逃げたくなるぐらいです。
藤岡:アジアっぽいですね。
ティラ:そうですね。携帯電話を持てたこの現代社会だから、彼女の介入をある程度避けることはできますが(笑)。でも彼女の干渉のおかげで孤独を感じないで済む、ということも確かです。少なくとも母親は自分を心配してくれている、という感覚、その心情的なサポートがとても嬉しいものです。それは失くしたくありません。自分の娘にもそういう姿勢でいたいと思っています。一線は尊重するとして。娘の一線は超えないようにしなくちゃ。
親というのはいつも子どもを気にかけています。18歳でも40歳以上でも、誰もが人の子です。そういう文化は残したいという一例です。私たちのアイデンティティ、ミャンマー人のアイデンティティです。
ソウ・モウ:文化としてのアイデンティティは、あえて発信しないと守れないのではないかと思うことがあります。ミャンマーのアイデンティティをどう人に伝えるべきか? 私は、他の文化やアーティスト、さまざまな芸術分野とコラボレーションするといいと思います。自国文化の価値は、発信する立場に立つとよく見えてくると思うのです。
ティラ:私たちは世界を相手にします。国際的なアーティストとの共同作業を実現させています。コラボレーションなら、いずれの参加者も自国のアイデンティティを失わないで、新しいアイデンティティを生み出せるのです。
先月、ボンド・ストリート・シアターとベン・ジョンソンの戯曲「ヴォルポーネ」を元にした共同創作をしました。イギリス人の書いた作品ですが、ミャンマーの現代社会に関わるストーリーにしました。そのふうにして、新しいアイデンティティを探っているのです。
原作では、強欲で悪どい金持ちが出てきます。彼は瀕死の病にあるフリをします。遺産相続人がいないから、遺言に名を載せてもらおうと下心のある男たちが土産物を携えて集ってきます。3人の人物が出てきます。弁護士、退役軍人、そして不動産屋です。結局遺産を相続するのは、金持ち男の使用人なんです。これが原作ですが、私たちは地元の視点を加え、1時間のところでストーリーを止めます。
藤岡:そこから観客とのやり取りを開始するのですね。そしてミャンマー社会の縁故主義や不平等についてテーマを進める。なるほど。
さて、最後に今回の日本訪問について感想を聞かせてください。
ソウ・モウ:今回初めての訪日でした。昨日はふたつの舞台作品を見ました。観察するだけで学ぶことがありました。舞台のセットの組み立て方、照明、最新技術の匠、そしてフェスティバルの場を利用する方法論。これからの数日の間に、各国各文化からさらに多くの人に会い、舞台作品を鑑賞したいと思っています。
ティラ:TPAMは全く新しい体験です。まだ学びの途中にあります。舞台芸術という産業が実際に成立しているということ、国際的な広がりを持っていること、そしてフェスティバルのスタッフやディレクターと対話をしなくてはいけない、といったことを学びました。いま私たちは現地公演を重視していますが、これからはミャンマー国外に舞台を広げていきたいと思います。世界に誇れる私たちの豊かなパフォーマンス文化を世界に知ってほしいです。
藤岡:ぜひ。今回のネットワーキングが未来に実りを多くもたらすことを祈っています。

【2017年2月13日、YCCヨコハマ創造都市センターにて】
インタビュアー:藤岡朝子(ふじおか あさこ)
映画配給会社を経て1993年より山形国際ドキュメンタリー映画祭のスタッフに。2009〜2014東京事務局ディレクター。2006年より韓国釜山映画祭のANDプログラムと助成金のアドバイザー。アジアのドキュメンタリー映画『長江にいきる』『ビラルの世界』を日本で国内配給し、アジアの映像製作者の合宿型ワークショップの連続主催を続ける。日本のドキュメンタリー映画『祭の馬』『三里塚に生きる』『FAKE』等の海外展開プロデューサー。
写真:山本尚明






