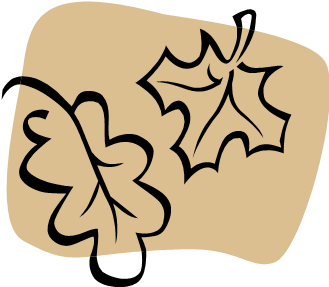春を歌えば
オザイおじいさんがシフン *1を奏でると、川は耳を澄まし流れを止め、傷ついた心は癒され、胡蝶蘭の花が咲き、鳥たちもシンフォニーを奏でる。これがおじいさんと竹笛がもつ魔法の力でした。
*1 アッサム州ボド族のボド語で竹製の横笛のこと。
けれども、その年のマドラガミ村では、大地はカラカラで、辺りは物寂しく、歌声も響かない春を迎えようとしていました。春の訪れを告げる雨はまだ到来せず、新型コロナウイルスのせいで春を歌う歌もお預けだったのです。だから、オザイおじいさんも、ただわびしく腰を下ろし、ボド族の新年バイサグ*2のお祭り騒ぎがないことにがっくりきていました。
*2 ボド語で「新年の始まり」という意味で、4月中頃のボド族の新年及びその時の祭りを指す。
今日もそんな物寂しい時間をオザイおじいさんは庭で過ごしていました。ふと向かいの家の庭に目をやると、サンタル族の小さな男の子が目に留まりました。前にも見かけたことはあったのに、これまでこの男の子に気づくことはまったくありませんでした。
男の子はとても小柄でがりがりで、小さな囲いのない庭のタマリンドの木の木陰の下に置かれたチャポイという縄編みの寝台の上に寝そべって、子ヤギに乳を飲ませる母ヤギの頭をポンポンと触っていました。横には犬が一匹前足にあごをのせ、地べたにペタッと伏せていました。
家の中には誰もいないようで、葦で編まれた壁の上のトタン屋根は、強風で角がめくれ上がっていました。庭ではメンドリたちがコッコッコッコッと喉を鳴らして、強い日差しに焼かれて乾いた地面に行きかう蟻をついばんでいました。
オザイおじいさんは、毎日この場所を目にしているはずなのに、自分がこの男の子に今の今まで全く気づかなかったとは、驚かずにはいられませんでした。
男の子は、オザイおじいさんに気が付くと、体を起こし黒い顔の中に白い歯を見せてにこりとしました。下は小さなふんどし一丁で、上にはかなりだぶだぶで穴の空いたベストを着ていました。オザイおじいさんもにやりと笑い返しました。おじいさんは少年のことが気の毒に思えました。
「ぼうや、ご飯食べたか?」
オザイおじいさんが大きな声で尋ねると、男の子は首を横に振りました。
「腹減っとらんのか。」
男の子がうんとうなずきました。
おじいさんはそれ以上聞くことはしませんでした。
代わりに大声で「名前はなんて言うんだ。」と尋ねました。
男の子は、「ジュグヌ」と答えました。
男の子は、犬を抱え上げて大きな声で「バトルー!」と言いました。
子供らしい元気の良いジュグヌを見ると、オザイおじいさんの顔には笑みがこぼれました。男の子は、家の中に入ると、バナナを一本取ってきてメスヤギに分け与えました。
「お母さんはどうした。」おじいさんは聞きました。
「いないよ。米をもらいに行ってる。」
「一緒には行かなかったのか。」
「だって遠いもん。キデンの学校だから。」
二人の会話はボド語とサンタル語を混ぜたものでした。そんな風に話していると、遠い昔ボド族とサンタル族がお互いに仲良く暮らしていたときのことがおじいさんには懐かしく思いだされました。でもボド族とサンタル族の間で争いが起きてからというもの、悲しいことに二つの民族社会はあれよあれよという間にそりが合わなくなっていきました。 その時の大混乱でオザイおじさんはたくさんの友を失いました。ジュグヌのおじいさんマルカスもその一人でした。ジュグヌのボド語とサンタル語を混ぜた話をつなぎ合わせて聞くうちに、母親のタラが支援物資をもらいにハルディバリ小学校へ行ったのだと合点が行きました。
「おまえ、学校は。」オザイおじいさんが聞きました。
「学校には行ってないよ。」
おじいさんは、男の子が学校に行ってもおかしくない年齢だと気が付きました。たぶん7歳。いや、8歳かも。
「なんで行かんのだ。」
ジュグヌは腰のふんどしの端をつまんでパタパタして見せました。
「これで学校へ行くのは嫌だよ。かあちゃんがズボンを買ってきてくれたなら行くけど。」
おじいさんは返す言葉がありませんでした。
焼けるような日差し。お空のてっぺんを過ぎた太陽。おじいさんの息子のお嫁さんのビバリが、パタン、パタンと音をさせて機織り機で腰巻布のガムサ*3を織っていました。ビバリは、手を止め立ち上がると、バイサグ用に用意しておいた卵を二つと、それにココナツフレークを散らした米蒸しパンをいくつか袋に入れると、庭の柵のところまでやってきて、ジュグヌを手招きして呼びました。ビバリが袋を差し出すと、ジュグヌが駆け寄ってきました。
*3 ボド族の男性が身につける丈が膝下まである腰巻布。
「遠慮せず食べなさい。」
ジュグヌは袋を受け取って中をのぞくと、うれしくて目を蛍のように輝かせました。ジュグヌ。なるほどね。だからタラはジュグヌ*4という名を付けたのね。
*4 「蛍」という意味のヒンディー語の単語。(訳者注)
どれほどビバリはジュグヌを自分の子供みたいに胸に抱き寄せてしばらくギュッとしてやりたかったことか。でも、保健所の人から「ソーシャルディスタンス」をと言われている。こんなかわいらしい子供が危険だなんてありはしましょうか。ビバリは言われたことに得心が行きませんでした。
ジュグヌが食べるのに合わせて、オザイおじいさんがシフンを吹き始めると、その音色はマドラガミ村のいらだつ熱気と土埃に、気を落ち着け脱力させるような小滝となって降り注ぎました。なんという魔法のような調べ。その音色に熱気はやわらぎ始め、ほこりも落ち着きを見せ始めました。
オザイおじいさんが竹笛を吹き続ける間に、ジュグヌはゆっくりとチャポイの上に体を滑り込ませると、バトルーの背中に頭をのせ、そばのメスヤギを触るので片腕をだらんと下ろし、もう片方の手の指についた米蒸しパンの最後の残りをぺろっと舐めました。オザイおじいさんが吹き続ける竹笛の柔らかい音色は、ジュグヌを眠りへと誘っていきます。ジュグヌに枕にされたバトルーさえ体を動かしません。ヤギは膝をついてチャポイの下から見守っています。みなジュグヌをそっと眠らせたのでした。
「なるほどなぁ。これならタラもジュグヌが一人ぼっちとは思ってはないな。」
そのうち向こうの方からタラが姿を見せました。頭には重そうな麻袋をのせていましたが、擦り傷のあるその足はきびきびと歩みを進めていました。おじさんには、タラがジュグヌのズボンを買ってきているようには見えませんでした。タラのサリーは、スカートのようにひだひだがついて垂れ下がっていて、上半身には色にグラデーションのある男性用のシャツを着ていました。たぶんサリーは、体半分のところで破れていたので、そんなふうに体に巻き付けていたのでしょう。オザイおじいさんは、パンデミックになるまで、命あふれる庭の中に、しかしとても苦しい生活の中にいるこの愛らしい少年と、そして雨風に耐えてきた若い母親の存在に気が付かなかったことを心苦しく感じました。
次第にオザイおじいさんとジュグヌ少年は、互いの庭から出てきてはもう一方の庭で一緒に過ごすのが日課になりました。雨はまだ降らないし、コロナも収束していない。オザイおじいさんには、バイサグ祭りでみんなの先頭に立ってはしゃぐことができないのがたいそう残念でなりませんでした。
おじいさんがシフンを吹けないぐらい落ち込んでいる昼下がりには、ジュグヌがチャポイの上に立って「ねえ、シフン!今日は吹かないの?」と元気に声をかけてくれます。ジュグヌはとても活気あふれる少年で、持つものはほとんどなかったけども、人に与えてくれるものの多い少年でした。
オザイおじいさんには、ジュグヌの頼みを拒むことなど考えられませんでした。なので、おじいさんはシフンを取り出すと唇に当て、ジュグヌはというと調べを聞きながら自分の家の庭で遊びまわるのでした。
それからジュグヌの動きが落ち、バトルーと一緒にチャポイに腰を下ろしにやってくると、それを合図にオザイおじいさんは笛の音を子守歌に変えます。するとジュグヌはバトルーの上にそっと頭を載せ、眠りに落ちて行くのでした。
世界中がコロナ禍と戦うための方策を探していましたが、そんな中でも自分の庭に蓄えておくべきものがこんなにもあるのだということにオザイおじいさんは気が付いたのでした。

あるときジュグヌの姿も声も見えも聞こえもしなかったことがありました。オザイおじいさんはそれだけで動揺しました。どうした、病気になったのか?
すると、母親のタラが愛しむようにジュグヌの小さな手を握って家の裏から姿を現しました。おじいさんは気が抜けるほどほっとしました。年が離れてはいたけれども、自分とジュグヌの間にはなんとも美しい絆が生まれていたことにおじいさんは気づかされたのです。
「今日は何を持ってきたんだい?」オザイおじいさんは、大きな声で声を掛けました。
「トウモロコシ!」
ジュグヌはそう答えると柵のところまで走ってきました。
「かあちゃん、トウモロコシ植えてたんだ。でも雨が降らないから芽が出ない。」
ジュグヌはチャポイによじ登ると、バトルーも上がるのを手助けし、言いました。
「かあちゃん、芋を掘ってたんだ。」
「取れたかい?」
ジュグヌは首を振りました。
「デンキヤ*5の柔らかい新芽も雨が降らないと生えないでしょ。ぼくとっても大好きなのに!森のタロイモやサトイモもどんどんなくなってきてるって。雨がすぐに降って来なきゃ、食べるものは米と塩だけだってさ。かあちゃんが言ってた。」
*5 クワレシダ。シダ類で新芽はゼンマイのように食することができる。(訳者注)
タラはロックダウンのせいで日雇いの仕事が見つからなくなっていました。商店の中にはわずかな食料品の在庫を置いているところもあるにはありましたが、タラにはそれを買うだけのお金がなかったのです。
「今日は飯食ったか?」
オザイじいさんが尋ねると、ジュグヌはうなずきましたが、「かあちゃんはまだ。」と付け加えました。
「そりゃどうして?」
「一人分しかなかったんだ。バトルーか、かあちゃんか。」
小屋の日陰にいるバトルーが葉っぱの皿に載せられたものを食べていました。
ビバリは、お米とジャガイモを袋に入れていたのを柵越しにちょうど置いたところでした。
「ジュグヌ!これ、お母さんに持っていってあげてちょうだいね。」
ジュグヌは、庭の仲間たちを引き連れて、すぐに柵のところまでスキップしながらやってきました。拾い上げると「かあちゃん!」と言って家の中に入っていきました。再び家から出てきたとき、ジュグヌは何かを手にして、オザイおじいさんに見えるように頭の上に抱えて来ました。
「なんとな!セルザ*6じゃないのか!」おじいさんは感嘆の声をあげました。
オザイおじいさんは胸の鼓動が高まりました。そのセルザが誰のものか一目でわかったからです。
「うちのじいちゃんが昔弾いてたんだって、かあちゃんが言ってた。」
壊れたセルザの音色は、オザイおじいさんの記憶の回廊をめぐって共鳴しました。自分とマルカスがバグルンバ*7を何度も一緒に踊ったバイサグの光景が目に浮かびました。そして、その後あの暴動が起きたのです。何年も前にこの暴動もコロナ禍と同じく、新年の楽しい気分を抑え込み、心の美しい二つの人々の間にくさびを打ち込んだのです。暴動が起きたのもバイサグ祭りの時で、みな命の危機を感じ家から出ずにいたのでした。
ジュグヌの声がすると、オザイおじいさんは白昼夢から呼び戻されました。
「かあちゃん、ぼくがいつか弾くかもしれないって、大切にとっておいたんだって。思い出のあるものだって。じいちゃんばあちゃんとのつながりは家にこれしかないんだって。」
ジュグヌは一瞬黙って、そしてオザイおじいさんに尋ねました。
「つながりってわかるよね。」
「で、つながりって何かね?」面白がってオザイおじいさんは尋ね返しました。
「つながりってねぇ」
ジュグヌは左手で右の手のひらを取り、自分の胸のところにそっと置いて「これさ。」と言いました。
「つながり。そうだな!」
小さなジュグヌが自分の家の庭で胸に手を当てているのを見ると、その道向かいの庭にいるオザイおじいさんは、胸がいっぱいになりました。
「お父さん、弾いてくれたんだろ。」
「とうちゃんのことは覚えてないよ。精霊がとうちゃんを連れて行ったとき、ぼくはまだお乳を吸ってたんだってさ。」
ジュグヌはセルザに目を落とすと、目を輝かせて尋ねました。
「これ直せる?そしたら一緒に弾けるかも。ね、じいちゃん。じいちゃんがシフンで、ぼくがセルザだよね?」
その日初めてジュグヌがオザイおじいさんのことを「じいちゃん」と呼びました。自分の祖父のように。
「できるさ。」
オザイおじいさんの声は震えていました。
「そうなりゃ、今まで一番楽しいバイサグ祭りになるな。」
「そうだね!」
ジュグヌは、チャポイから飛び降りながら笑いました。そして、壊れたセルザを高く掲げ、バイサグの歌を歌ってバトルーと一緒に喜んではしゃぎだしました。
ジュグヌは、一瞬動きを止めると叫びました。
「じいちゃん!シフン吹いてよ!」
「よしきた!」
オザイおじいさんもそう言葉を返すと、中庭へ踊りながら出ていきました。オザイおじいさんのとてもうれしそうな様子を見て、おじいさんの息子も太鼓を取り出してきて、トントコトン、トントコトンとリズムよくたたき始めました。
怒りを突き刺してくるような日の光がついに地平の下に消え去ると、オザイおじいさんは、笛の調べを変えました。それは、干上がった大地の渇きをいやしてほしいとばかりに空を言いくるめるような甘い音色でした。
たいそう魂の籠った音色だったからか、竹笛の旋律を聞いた一羽のカッコウが、オザイおじいさんの奏でる音色に合わせて、空よ、慈悲を見せて、雨を降らせて、と懇願するかのように声高らかに鳴き始めました。タラとジュグヌのために、そして、おなかを満たしてくれる一回一回の食事を、晴れの祭りそのものとしてバイサグ祭りよりもずっと楽しみにしている人たちのために。 とどろき渡る太鼓の音に竹笛、そして、カッコウの鳴き声の三重奏が発する情熱は、マドラガミ村全体とその上に広がる空とを突き抜ける波動を生み出し、天さえもその身を震わせ始めました。すぐにドンドコドンと太鼓の音が村のあちこちで共鳴し始めました。突然、太鼓とは違う、ものの唸るような音がオザイおじいさんの耳に聞こえてきました。おじいさんは、天の身震いが聞こえたかと思いました。
その音は、遠くの方からだんだんと近づいてきます。ゴロゴロと鳴るその音は、近づくにつれどんどん高まり、次の瞬間、耳が聞こえなくなるぐらいの大きな音となって、みなの頭上でドドドーンと鳴りました。
オザイおじいさんは、うれしくて飛び上がりました。
「雷だ!」
オザイおじいさんは、自分の願いが聞き入れられたという予感を感じながら、無意識のうちに深い喜びの音色を奏で始めました。その感動的な調べは頑固一徹の空を切り裂き、ついに空から涙のしずくを引き出しました。そして、天空から零れ落ちる涙は、渇きを癒すように乾ききった大地の上に降り注ぎました。バイサグがマドラガミ村に到来した瞬間です。
*6 ボド族の伝統的な4弦の小さなバイオリンのような楽器。
*7 ボド族の祝う新年であるバイサグの時に踊られる民謡。
「雨だ!雨だ!」ジュグヌは喜びのあまり飛びあがりました。
ビバリも中庭に走って出てきました。大粒の雨がビバリの顔にぱたぱた当り、唇へと流れ落ちていきます。春の最初の雨の味を確かめようとビバリは閉じた唇を開きました。マドラガミ村のあちこちで、おのおのの家の中庭からバグルンバを歌う声が沸き起こり、その歌声は同じ空の下で一つに集まってきて、同じ春を讃える歌を奏でる一つの声となり、大気を満たしていきました。
ああ、春よ!
どの家の人たちも自分の家の中庭にいたままでしたが、おのおのが別の場所にはいても、心は新年を祝うため寄り添いあい、みな一つになって歌い踊ったのでした。
ジュグヌの声は、うれしさから雨と太鼓の音以上に大きな声となって、ボドの人たちとバイサグの歌を歌いました。
「バグルンバ、ハイ、バグルンバ!」
オザイおじいさんは、ジュグヌとタラと出会ってから初めてタラが嬉しそうにしているのを目にしました。ジュグヌと一緒に手を取ってくるくる回るタラの眼には、喜びの涙が流れていました。
タラが植えたトウモロコシもようやく芽が出ることでしょう。デンキヤもくるっとした柔らかい新芽をのぞかせ、サトイモとタロイモにも新しい茎が伸びてくることでしょう。
ビバリもタラも自分の家の中庭で踊りました。二人は別々の庭にいましたが、二人が踊る歌は同じ歌でした。春の歌!命が息を吹き返す歌!二人がかわいがる小さな男の子も、二人を濡らす雨のように同じです。
春の歌を歌う雨の合間からオザイおじいさんの耳に入ってくる声の中には、友人たちの声もありました。みな自分の家の庭から歌っています。
ビバリは、腰巻のガムサをすでに織り終えていました。一枚は自分の夫に、一枚はオザイおじいさんに渡します。そして、もう一枚、小さい特別な腰巻は、ジュグヌに。
そして、春の歌は、あたり一杯に広がり、孤独を打ち負かしてくれたのです。