サラ・モニカ(以下、サラ): ローカルな催しや国際的なスケールのイベントもあわせて、現在、どれくらいの文芸フェスティバルがインドネシアで開催されているのでしょうか。
ユシ・アヴィアント・パレアノム(以下、ユシ): フェスティバルという言葉はとてもフレキシブルでさまざまな活動に用いられます。毎年定期的に行われている文芸フェスティバルは限られており、ほとんどは不定期開催なので、正確に数えるのはちょっと難しいですね。フェスティバルに携わる人々は、やる気、関心、愛情をもって文学的活動に取り組んでいるのですが、困難に直面すると後退してしまいます。というか、一度開催したきり、そのあとがなくなってしまうのです。
いまも活発な文芸フェスティバルと言えば、ウブド・ライターズ&リーダーズ・フェスティバル(UWRF)、マカッサル国際作家フェスティバル(MIWF)、ジャカルタ国際文芸フェスティバル(JILF)、それからサリハラ・コミュニティの文芸とアイデアのフェスティバル(LIFEs)、ボロブドゥール・ライターズ&カルチュラル・フェスティバル(BWCF)、それから我々の協力者であるイルワン・バジャンとウインディ・アリエスタンティがイニシアチブをとるパチャ-ル・メラ(Patjar Merah)です。彼らはブック・バザールにも参加しています。パチャール・メラは、巡回型のリテラシー・フェスティバルで、いわゆる文芸フェスティバルではなく、街から街を巡って読み物へのアクセスの均等化を推進する、まさに読書リテラシー向上のためのフェスティバルです。ユニークなのは、彼らはこのフェスティバルの費用を、手に届きやすい廉価で書籍を販売するブック・バザールを開催することで、自助的(セルフサステナブル)に捻出していることです。また、普段から、普通展示会には使われないような場所を利用します。ジョクジャカルタでは倉庫を、マランでは野外映画上映の跡地、スマランで観光エリアの旧市街などです。
本来ならもっと多くの場所を巡回する予定だったのですが、残念ながらパンデミックが起きてしまって。ほかにパチャール・メラがユニークなのは、多くの作家やミュージシャン、映画制作者などをフェスティバルに招いている点でしょう。
カリマンタンにはアルフ・サストラ(Aruh Sastra)という興味深いフェスティバルがあります。「アルフ」というのは、宗教的な宴を表す地方語で、パチャ-ル・メラ同様にあちこちを巡回しています。スラウェシやビンタン島にも同じような活動があります。
ただ残念なことに、こうしたほとんどのフェスティバルがパンデミックでとん挫してしまいました。公式なデータはありませんが、影響を受けたのは数十件ほどでしょうか。例年継続的に開催されているのは10件もないでしょう。
サラ: こうした文芸フェスティバルがインドネシアで盛んになる理由は何だと思われますか。
ユシ: 各フェスティバルがしっかりしたアイデンティティをもっているからです。文芸フェスティバルのなかには、まだ個性がなく、どちらかというと作家同士の会合といったものもありますが。しっかりしたアイデンティティをもつフェスティバルの一つはMIWFでしょう。(首都から離れた)インドネシア東部の作家たちや、その豊かな世界を世に知らしめることを目的としています。当初、彼らの活動拠点はスラウェシ島でしたが、現在はさらに広がりを見せています。
一方で、JILFは南半球の作家たちが一堂に会するフェスティバルです。こうしたアイデンティティが、それぞれのイベント開催の根拠となっているのです。簡単に言うと、潤沢な資金があったとしてもJILFがJ.K.ローリングのような作家を招待することはありません。JILFは南半球の作家たちのための交流の場だからです。JILFはアジア・アフリカと、さらには南アメリカのスピリットを大切にしています。UWRFは、テロによる爆破を受けたあとのバリの経済を立て直すために始められました。バリは観光の要素が強いですから。これらの文芸フェスティバルは文学的要素も互いに異なっています。それぞれに独特な賑やかさがあり、フェスティバルに足を運んだ人は、その特色を知ることになります。
サラ: JILFを立ち上げた経験から、文芸フェスティバルの最大の試練は何だと思われますか。
ユシ: 新しいことを始めるということです。ジャカルタではフェスティバル自体はめずらしいものではありませんが、実はJILFの主催者であるジャカルタ芸術協会は、JILF以前は文芸フェスティバルを実施したことがありませんでした。最大の試練はスタミナを維持することですね。追加の資金を得るのには、文芸フェスティバルがすでに知られているほうが容易ですから。
私たちはあちこちの大使館や企業や、招待する作家たちを訪ねて回って協力を求めました。すべての作家が協力してくれたわけではなかったのは、JILFがどういうものかを知らなかったからでした。イベント終了後、多くの作家たちが私に直接手紙をくれて、JILFに参加しなかったことを後悔したと伝えてきましたよ。私たちは教育文化省とジャカルタ州知事に対し、JILFの意義を説明し、文芸界でジャカルタの知名度があがることを説得する必要がありました。最後に売り込んだのは、フェスティバルの明確なコンセプトと、我々主催団体に対する世間の評価です。
サラ: すでに名を知られ、継続的に開催されてきたBWCF、MIWF、あるいはUWRFなどについて、最大の試練は何でしょうか。
ユシ: 彼らの立場を代弁することはできませんが、聞くところによると、毎年財政上の問題が一番の悩みのようです。おそらくUWRFは協力者も多く、すでに比較的に安定しているでしょう。ほかのフェスティバルは、地元自治体の協力を得られなかったり、行政手続き上の問題に阻まれたりするなどがありますね。そのほかにも、スポンサーに依存して自立できないフェスティバルは、行きつくところ継続は危うくなります。どこも自力でやっていけるかどうかが最大の試練なのです。ですから、当初から自立を目指して真剣に取り組んできたパチャール・メラのようなフェスティバルを見ると、とても嬉しくなります。
サラ: 資金の問題のほかに、フェスティバルが続かなくなってしまう原因はありますか。
ユシ: 一つめに、資金の問題は絶対です。二つめは組織の問題です。それぞれの組織が1度きりのイベントのために編成されたのか、それともその後があるのか。もしあとがあるとすれば、今年のことだけではなく、5年先、10年先についてのビジョンがあるべきでしょう。単に「好き」という意識に基づく「アマチュア」的なコンセプトのイベントは、フェスティバルの運営自体もそういった気持ちや、やる気からスタートすることになります。しかし、文芸フェスティバルの運営はやる気だけで何とかなるというものではありません。
サラ: コロナの影響で、文芸フェスティバルやアート関連事業は活動を阻まれています。それでもコロナの時代に対応し、活動を継続しているところもあるようです。これからの文芸フェスティバルはオンラインに切り替わっていくのでしょうか。
ユシ: 私が知る限り、オンラインになったものも、一時休止しているものもあります。JILFとパチャール・メラ、それからUWRFはオンラインに切り替わりました。MIWFは昨年一旦休止しましたが、 今年はオンラインになりました。パチャール・メラも同様ですが、今年も依然活気があります。出版に関して言えば、私も出版に携わっていますが、まだまだ盛んです。いくつかの小さいフェスティバルは延期になりましたが。フェスティバルという言葉は“festive”、すなわち「賑やかさ」という語から来ています。直接的な相互交流という点から言えば、オフラインとオンラインでは確かに大きな違いがあります。直接交流できるリアルなイベントの場合、例えば特定のセッションを目的に訪れたとしても、新しい発見や、新たな出会いが得られ、一段と魅力的なものになるでしょう。つまり、オフラインで行われる場合のほうが、より多くの可能性を生み出すだろうということです。一人の作家がほかの作家に出会うことが、さらに喜ばしい活動に発展してゆくことがあり得るのです。新しいアイデアやチャンスがあるのです。一方オンラインだと、熱気のようなものがだいぶ違います。意味がないというわけではないのですが、とても違っているのです。

サラ: あなたご自身は、文芸フェスティバルが、インドネシアのリテラシー文化に与える影響はあるとお考えですか?
ユシ: とても広い質問ですね。評価できる点は、文芸フェスティバルを訪れた人たちに、それぞれの地元でもフェスティバルを開催しようという意欲をもたらしていることでしょう。仮にフェスティバルとともに本のバザールが開催されるなら、リテラシー文化のみならず財政面での効果もあがるでしょう。つまり関連産業も利益を得ることができるということです。各種フェスティバルに共通することとして、若手でポテンシャルのある書き手の発掘に力が注がれていますが、広く知られるようにはなっていません。MIWFやUWRF、そして JILFでも、評者によって有望と認められながらもあまり知られていない書き手たちに活躍の場を与えようと常に試みています。一方、「インターナショナル」というタイトルを冠している文芸フェスティバルだと、インドネシア国内の作品が世界的に知られるきっかけになるのかもしれません。ただ、まだそうしたフェスティバルは始まって間がなく、影響を評価できるまでにはなっていないのでしょう。フェスティバルで知り合った作家同士がその後協力してプロジェクトを始めるということはあります。ですから、文芸フェスティバルのもたらす効果は、産業的側面と知的生産の面から見る必要があると思います。
JILFは知的生産の分野に特に力を入れています。JILFに参加する作家たちには講演原稿の作成が義務付けられます。このイベントを通じて知的生産を行いたいからです。ただ賑やかで、楽しく、作品だけ読んだらあとは何もないというイベントではないのです。BWCFもこのことには真摯に取り組んでいて、文化や宗教間対話などの素晴らしい論考が用意されています。フェスティバルそのものに参加ができなくても、フェスティバルで新たな知見が発表され、それを手に入れることができます。毎年ルーティンとして開催されるだけのイベントではないのです。
サラ: 文芸フェスティバルは読むことへの関心を高めると思いますか。
ユシ: これについては一言あります。インドネシアでは読むことへの関心が低いとたびたび言われますが、一体何をもってそう言うのでしょう、何に基づく評価なのでしょうか。フェスティバルが盛況でなかったことはないし、ビッグ・バッド・ウルフのような書籍販売のバザールもいつも賑わっています。来場者は中間層の人々ばかりと言っても、バザールは24時間営業していますよ。なぜ人々はカート一杯になるほど熱心に本を買うのでしょうか。つまりこれは、書籍へのアクセスに問題があるのです。読書への関心がないわけではないけれど、知的資源へのアクセスが必ずしも平等なわけではないということです。
インドネシアでは読むことへの関心が低いという人は、パチャール・メラを見ると、それが間違いだということがわかるでしょう。読み物へのアクセスが簡単にできるのはジャワ島、とりわけジャカルタに住む人々で、カリマンタンや東部の島々の人々の手には届きにくく、読み物へのアクセス自体が容易でないというのが実情です。遠隔地への本の輸送が決して安くないことからもわかるでしょう。時として輸送費のほうが書籍そのものよりも高額になるのです。このような状況のなか、パチャール・メラのようなフェスティバルは、読者に本を届ける一つの手段になり得ます。読み物への関心が低いと言われますが、書籍バザールのあるイベントには毎回何万人もの人が訪れ、たくさんの本を買ってゆくのです。購買者も大学生や中高生だけでなく、主婦や非正規に働く労働者も来ます。彼らはそれまで実際に目にしたことのなかった本を手に入れることができるのが本当に嬉しいのです。
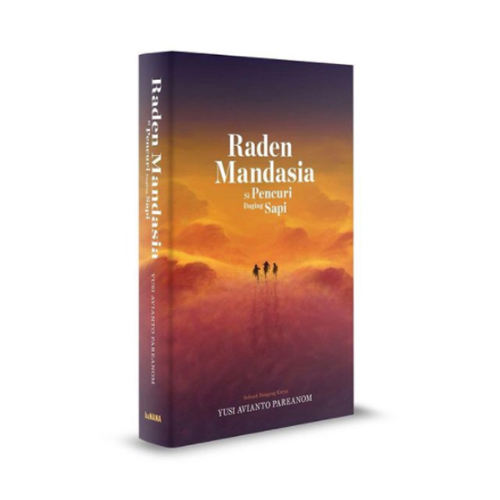
サラ: 文芸フェスティバルの開催はインドネシアの政治や社会に影響を与えていると思いますか。
ユシ: そうした事柄について声を上げているフェスティバルはいまのところはありません。私たちはあらゆるテーマを取り上げます。目下、あまりに多くの情報が我々の関心を引いていますから。特定のテーマを議論しているのは、それに関心をもつ一部の人たちです。それ自体も細分化されていますが。社会や政治の問題に取り組むために、文芸フェスティバルが大規模に人々を動員できるかどうかについては、否定的です。 個々人や小規模なグループの意識を変える、もしくはインスピレーションを与えるといったことは、すでにできていると確信しています。マランで行われたパチャール・メラのフェスティバルが、東ヌサ・トゥンガラから来た人たちに、(彼らの地元の)バジョでイベントを行おうというインスピレーションを与えたように。革命のような事態を除き、大きな変化は常に小さな一歩から始まるものです。
サラ: インドネシア国内の政治や社会の問題が文芸フェスティバルに影響した事例はありますか。
ユシ: ありました。80年代から90年代にかけての政治社会状況は「サストラ・コンテクスチュアル* 」について話し合うフェスティバルを生み出しました。宗教が活発化した状況においてイスラーム文学祭が開催されたこともあります。政治や社会の問題がインスピレーションを与えるのではなく、むしろ妨害してしまうケースもありました。少し前にもUWRFが、左派の潮流、あるいはインドネシアのコミュニストの歴史をテーマとしたセッションを設けようとしていたことがありましたね。しかし結局禁止されました。それから以前ジャカルタで、「左翼は今もゆく(“Kiri Jalan Terus”)」と題するフェスティバルがありましたが、これも禁止されました。権力者だけでなく宗教団体からの妨害もあります。例えばFPI イスラーム防衛戦線のようなグループが、カナダからレズビアンの作家を招待して開催されたイベントを解散させたことがありました。ある社会グループが、例えば文芸フェスティバルを開催する別の社会グループによる表現活動を妨げようとするときに困難が起こるのです。これは深刻な問題です。
* サストラ・コンテクスチュアルとは、80年代のインドネシアで提唱された文学潮流。文学作品の価値に普遍性はなく、それらは常に社会的、空間的、時間的文脈に決定されるという考えに立つ。(訳者註)
サラ: パンデミックはいつ終わるかまだわかりませんが、これからも数々の文芸フェスティバルは存続してゆくでしょうか。
ユシ: 私たちが同じように良い方向に物事を考え、いつかパンデミックは終わるというポジティブな考えに立つなら、フェスティバルは再び動き始めると私は思います。誰もが直接会い、分かち合うことを渇望しているからです。その証拠に、パンデミックであってもフェスティバルはずっと続いています。このパンデミックは私たちに、本当に大切なものにこそ注力するべきなのだということを教えてくれました。
つまり、大した影響をもたらさない活動なら、大きなエネルギーを使う必要はないということです。パンデミック下ではあらゆることが起こりえますから。文芸フェスティバルでもさまざまな騒動があります。例えば、なぜAは招待されたのにBはされていないのかとか、なぜテーマはAで、Bではないのか、といったことです。誰のためにもならず、ただ争うことだけが目的のような諍いが常にあるものです。
サラ: 少し話を戻し、ジャカルタ国際文芸フェスティバル(JILF)がインドネシアで行われるようになった経緯についてお話しいただけますか。
ユシ: JILFは2019年に初めて公式に開催されましたが、着想はその2年前でした。まず優先したのは誰が組織に加わるかで、それからいつ、どこで、誰を招待するかを考えました。そのあとでようやく費用について考えました。開催の体裁を整えるまでに2年かかりました。ただふらっと来て、作品を読むためだけのイベントなら簡単です。しかし、まとまりと一貫性のあるイベントは一人の頭だけでは創れません。ですから当時チームの結束が固く、多くのボランティアの協力が得られたのは幸運でした。
サラ: 2019年に始まったばかりでパンデミックに見舞われたのは残念でしたね。
ユシ: 実は2020年の実施については、仲間たちと動き、協力してくれそうな組織ともすでに渡りをつけていたのです。準備は万端で、招待する予定の作家たちのクオリティーも楽しみなものになりつつあったので、予定どおりに実施できなかったのは本当に残念でした。昨年度はセミナーをオンラインで実施しましたが、熱気が違っていたということは認めざるを得ません。
サラ: 人選やテーマを決めるプロセスはどうなっていますか。先ほどのお話にあったとおり、ある作家は参加し、ある人は参加しないということで抗議を受けることもおありかと思うのですが。
ユシ: JILFのプロセスはとても民主的に進められます。フェスティバルのアイデンティが決まったら、テーマ、イベントの形を決め、パネルごとにシンポジウムを企画します。ジェンダーバランスも考えなくてはなりません。参加者は国内外から人選します。そのほかに、いくつかの団体からもバランスよく参加してもらいます。シンポジウムのテーマは全員が納得するまで話し合いますし、連日スピーカーが話すサブテーマの決定も慎重になされます。決定事項を発表すると、選ばれたスピーカーについてのコメントや意見が寄せられますが、参考として真摯に受け止めます。一見すると「つまらない」テーマもありますが、ほかのサブテーマを繋げる役割を果たしうるものとして検討します。
サラ: フェスティバルがそれぞれの作家に及ぼす影響はどのようなものでしょうか。
ユシ: ローカルな規模で言うと、出版者から注目されるようになることでしょう。フェスティバルに参加した時点で本が出版されていたら、その売れ行きが伸びることにもなるでしょう。作家たちは新しい場所で新たなインスピレーションを得ることができます。国際的な文脈で言えば、私たちはインドネシアの作家を諸外国に知らしめることはまだできていません。ですから、JILFでは「文学エージェント」という講座をもうけています。インドネシアでは文学作品を扱うエージェントの数が限られていて、3、4社しかないからです。すでに世界的に売り出されるインドネシアの作品もありますが、全体から見るとほんの一部です。
作家はフェスティバルから多くを学ぶことができると思います。ただのお祭り騒ぎではなく、シンポジウムがあり、一人の作家のアイデアが別の作家のアイデアと対峙し、ぶつかり合う場となるのですから。それぞれの意見に賛同するしないにかかわらず、このような経験は、学びを深める意欲さえあれば、作家自身の知識を豊かにします。常に注目を集めていなければ気がすまないというタイプの作家でなければ、きっと多くを学ぶことができるでしょう。作家がこのような文化的なイベントにオープンな気持ちで臨めるのであれば、自分自身を謙虚に振り返る機会にもなると思います。そして、「私よりずっと優れた人たちがまだたくさんいて、たとえ年齢は私より若くても、彼らから学ぶべきことがたくさんある」ということに気づくのです。 このような学びを得るなら、その人はその後、さらに広い見識をもつ作家になれるでしょう。
フェスティバルでは驚くべきことも知り得ます。2019年、私たちはボツワナからゲストを招きました。ボツワナでは本の出版が非常に難しく、作家は政府による学校用の教科書や読み物の注文に対応しなくてはなりません。また、作品は何度もの選考を経て、ようやく出版されます。ボツワナでは500部も売れれば「ベストセラー」とみなされるのです。自費出版ができる我々と比較してみてください。自分たちがボツワナの人々に比べていかに特権的かということに。当たり前なことに、感謝すべきと気づきます。
サラ: フェスティバルが存在することで作家たちは自作をより多く売ることができるのでしょうか。
ユシ: ええ。ビジネスのロジックに従うなら価格はより安くなりますよね。読者が作者に直接対面できる機会でもあります。とはいえ、フェスティバルでの販売数は大量というわけではなく、せいぜい10部から1,000部の間です。しかし、書籍販売という観点から言うと、フェスティバルは宣伝の機会にはなり得ます。どのような体裁でフェスティバルが運営されるかによりますが。
サラ: フェスティバルは、出版社にとっては出版につながりそうな作家を知ることができる場ですよね。出版社を経営されていますが、そういった作家をターゲットにされていますか。
ユシ: 招待した若手作家の作品を本にしたフェスティバルもあります。出版歴が1冊か2冊、あるいはまったくなく、メディアに作品を掲載しているような作家たちです。ウブド・ライターズ&リーダーズ・フェスティバル(UWRF)やマカッサル国際作家フェスティバル(MIWF)等が出した本から、出版社は誰にポテンシャルがあり、自分たちの方向性に合っているかを知ることができます。私の言うフェスティバルにおける知識の生産とはそういうことです。
出版社はさまざまな手段を通じて書き手を探しますが、フェスティバルはその一つですね。作家は特定の出版社と契約することもあるでしょうし、ジャカルタ芸術協会の文学懸賞もあります。入賞者の作品は出版にふさわしいかどうかわかりますから。現在ではブログの執筆者に注目している出版社もあります。Wattpadなどの書き手ですね。もちろん出版社がどのような作品を探しているかにもよります。フェスティバルで新たな書き手を発掘できなかったとしても、出版社は新しい仲間、人材と知り合えます。その関係がいい形で継続すれば、無償のエージェントとして宣伝してもらえることもあります。しかし、結局は作品の質次第です。出版社というものは、ただ作者と知り合いだという理由だけで取るに足らない作品を売り出して自分たちの評価を下げるようなことは決してしません。
サラ: 現在はデジタルの時代で、オンラインで本を出版し、販売することが容易になりました。デジタルの時代にあって、フェスティバルはどのような影響を受けるのでしょう。
ユシ: むしろ、フェスティバルがいかにしてデジタルというプラットフォームを有効活用するのか、ということかと思います。SNSによってイベントの盛り上がりや、フェスティバルのあとの余韻を継続させることができます。例えばフェスティバル前のティーザー広告やポスターは、人々の参加してみたいという気持ちを高めます。デジタルプラットフォームの有効活用の例ですね。それだけでなく、イベントが終わったあともフェスティバルの興奮をSNSでシェアできます。私はこれを障害物ではなくむしろフェスティバルを強化することのできる装置の一つであると考えます。もちろんリアルなイベントはほかには代えがたいものです。しかしオンラインのイベントにも、例えばZoomを用いて話すことができるなど、独自の利点があります。リアルなイベントの温かさをオンラインに求めることはできませんが、これはアナログ世代である私の見解で、すべての意見を代表するわけではありません。
サラ: デジタル書籍と印刷書籍に関して言うと、デジタル書籍に特化した出版社はありますか。おそらく価格も異なると思いますが。
ユシ: 現在ほとんどの出版社が印刷版とデジタル版を有しています。しかしインドネシアでは印刷書籍の点数のほうがデジタル書籍よりはるかに多いですね。少なくとも私の出版社を含めたいくつかはそうです。読者はまだ、本を手にすることのほうが好きなようです。確かに購入にはデジタルのプラットフォームがよく利用されていますが、実物を入手し、インスタグラムのようなSNSで本を持っているところを見せびらかすのが好きな人もいます。独特の誇らしさがあるのでしょう。希少な本であるならなおさらですね。

以前は、本を買うためには書店を訪れていました。現在はオンラインの再販業者が多く、値引きもあります。一番の違いは、店舗はスペースが限られているため本棚に展示されている本の数が限られることでしょう。本が売れなければ倉庫行きですが、本によっては売れる機運、タイミングのようなものがあります。ようやく話題になり始めた頃には、すでにその本は書店にはないということもあります。現在ではソーシャルメディアのおかげで書籍は常にオンライン上にストックされています。SNSを通じて多くの本が売れれば、得をするのは独立系の出版社ですね。以前と違い、自分たちでストックを持っていますから。
彼らを通せば取次業者は不要ですし、これまでとは異なる方法で読者にリーチしている場合もあるでしょう。以前なら、好む、好まざるにかかわらず大手の書店を介さなければなりませんでしたが、デジタル化は本の流通の仕組みそのものを変えました。
最近コミュニティベースの書店が登場するようになって、読者たちはもっぱらそうした新しい場所を好みます。フェスティバルに来るのが好きな人々も同じです。若い人たちには作者に会えて、本を手に入れることができるだけでなく、世界中に「自分はこの重要なイベントに参加したのだ」ということを見せたいという気持ちも否定しがたくあるのでしょう。自分が崇拝している人物がいる文芸フィスティバルに参加したら、誰もが当然誇らしい気持ちになりますよね。取り残されてはならないという気持ちに駆られるのでしょう。このような動機であっても、フェスティバルを盛り上げ、本の購買につながる以上大切です。最初は表面的であっても、きっと彼らはやがて熱心な読者になってくれると信じています。
サラ: それは、参加のための参加になっている一部の若い人たちに対する批判でもあるのでしょうか。
ユシ: 私はそうした若い人たちが来てくれるのは喜ばしいと思っています。大事なのはとにかく参加してみること。そういう若者たちもディスカッションに参加してみるところから、読書に対する興味を広げていくと信じています。彼らはきっといろいろなことに関心をもつはずです。フェスティバルにはインスピレーションを掻き立てる興味深いことがたくさんありますから。例えばハル出版社が東アジアの文学を取り上げて開催しているフェスティバルは、村上春樹のような有名な作家に限らず、同地域の作品に関してかなり深い知識を提供してくれます。驚きますよ。アクセスさえできれば誰もがフェスティバルを楽しめるのですから、アクセスの平等化はまさに共通の課題と言えるでしょう。東アジアの文学、西ヨーロッパの文学、ラテン・アメリカの文学など、人によって興味や関心の向きは違っても。
サラ: 最後に、今後インドネシアの文芸フェスティバルに望むことはありますか。
ユシ: 私の希望はごく標準的でありきたりなものです。インドネシアの各地でさまざまなフェスティバルが継続的に、プロフェッショナルに行われ、そうしたフェスティバルから新しい知識が生み出されることを願っています。そうすれば、社会や政治状況へのフェスティバルの影響に関する先ほどのあなたの問いにも、答えを出すことができるでしょう。
インドネシア語からの翻訳:竹下愛






