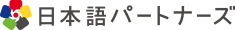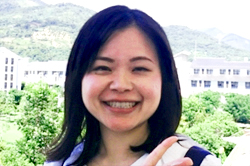台湾の高校では歴史の授業で世界史と台湾史を学びます。日本は時に世界史、時に台湾史として登場します。教科書には豊臣秀吉や織田信長といった見知った名前もありますが、知らない日本人の名前が多くあります。みなさんは「磯永吉(いそえいきち)」「末永仁(すえながめぐむ)」という名前を聞いたことがありますか。彼らは台湾では「蓬莱米の父」「蓬莱米の母」と呼ばれています。

そもそも蓬莱米とは、日本統治時代の台湾において品種改良に成功した米の品種で、粒形、大きさ、食味が日本産米とほぼ等しい米です。明治時代後期以降、日本は近代化に伴い、急速に農業人口が減少、主食である米を自国生産分では補えなくなっていました。そこで目をつけたのが当時植民地にしていた台湾。元来、台湾で食べられていたインディカ米は日本人の味覚にあまり合わなかったため、台湾で日本人の味覚に合うジャポニカ米を生産しようとしました。ただ台湾は日本より気温が高く、日照時間も長いことから生産は困難でした。そこで磯と末永は10年以上にわたり研究に研究を重ね、台湾で生産できる蓬莱米を生み出しました。それにより、台湾における水稲二期作栽培が容易となり、生産量・農家の収入ともに増加しました。彼らの功績が認められ蓬莱米の父と母として台湾の教科書に載っています。

台東にある池上という場所は米所で、池上米はおいしいお米の代表格です。調べてみると、池上米は蓬莱米の子孫だということがわかりました。台湾のおいしいお米の誕生の基には2人の日本人がいたというのは大きな発見でした。当時の日本にも、台湾にも有益な研究をした2人が日本の教科書に載っていないことは残念ですが、知ることができて本当に良かったです。教えてくれた歴史の先生に感謝です。