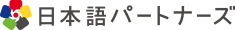マガンダン ハポン(タガログ語でこんにちは)。フィリピン・マニラ首都圏に派遣されている酒井忠喜です。
派遣されてから2か月になります。今回の派遣に伴い、初めて海外で生活をすることになったのですが、フィリピンでの体験から、海外で暮らすことについて、私が気づいたことを分かち合いたいと思います。海外旅行は、観光地を巡ったり、美味しいものを食べたり、お土産を買ったり等、日常の生活と異なる非日常の体験です。それに比べ、海外で暮らすことは、日常の生活をおくる体験だと感じています。
授業のある日は、ジプニーという乗り合いバスを利用して派遣先校へ向かいます。昼食は学食で食べ、1日2回朝夕と自炊をして、食べています。運動不足にならないように自宅でストレッチしたり、ショッピングモール内にあるフィットネスクラブでヨガをしたり、就寝は、次の日に備えて日本にいた時よりも、少しだけ早めに寝るようにしています。食事、運動、睡眠という日々の積み重ねです。もちろん、日本では味わうことのできないフィリピン料理を食べたり、派遣先校の生徒たちとやさしい日本語や英語で会話もしたりします。この派遣期間を終えた後にフィリピンでの体験は非日常の世界であったと、振り返る日がくるのかもしれません。けれども、現在の私にとって、海外生活は日々、生活する日常の世界です。
では、同じ日常でも、日本にいる時とは何が違うのでしょうか。それは、外国人として生活するということです。つまり、外国人というマイノリティとして暮らすということです。派遣先校では派遣期間である8か月間、日本語パートナーズという私の存在のために親切に接してくれます。生徒たちは会うたびに満面の笑顔で挨拶してくれますし、先生たちからも「Hi sensei!!」と日本語で挨拶されます。マイノリティであることがプラスとして働いています。一方、フィリピンでは公用語に英語が含まれますが、職員室の中でも、生徒同士の会話でも、ここマニラ首都圏の中に位置するバレンズエラ市では、タガログ語が使用されています。自分が全く意味の分からない言葉に囲まれていることになります。(私に話しかける時は英語で話しかけてくれる配慮はしてくれます。)自分には会話の内容がわからない、文化的背景もわからないので、面白い話が話されていても、雰囲気は伝わってきても内容はわかりません。外国語に囲まれて生活するということは、こういうことかと感じる時です。
帰国後、私は今回の経験を活かして、外国にルーツのある生徒たちの学習支援をしていきたいという希望をもっています。そのために、今回の経験は貴重な経験になると思っています。派遣前まで、日本の公立小学校に長年勤務し、クラスの中には、外国籍の生徒も受けもってきました。けれども、彼らの置かれている状況を理解し、彼らの気持ちに寄り添えていたかいうと、心もとありません。私はその困難さを想像はできても、自分ごととして捉えていたとは言えなかったでしょう。また、彼らの中には、本人の希望ではなく、親の都合で日本に連れてこられた生徒もいました。意欲をもって日本語を学ぶ気持ちになれなくても、仕方のない環境にいたわけです。わからない言葉に囲まれる生活であっても、大人である私は、これまでの経験から、ある程度状況を判断して生活することができます。けれども、まだ日本での生活経験がない外国にルーツのある生徒にとっては、小学校の高学年であっても、起きていることが、わからない状況だったのだと思います。
日本という外国で暮らしていくことに充実感をもって生活していくためには、親以外にも支えてくれる大人が周りにいること、クラスの中に友達ができること、すなわち、人とのつながりの中で生きることだと思います。そこには言葉の壁が大きくそびえたつわけですが、残りの派遣期間の生活の中で、派遣先校の生徒や先生方以外にも、地域での人とのつながりを作っていき、その経験を帰国した後に活かしていきたいと思っています。