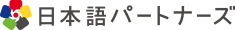これは今から半世紀以上前に書かれた、思想史家丸山真男氏の有名な評論のタイトルです。江戸時代から昭和に至る、日本人の価値観における大きなパラダイムの変換を指摘した、画期的な文章です。その指摘は21世紀の今も、なお色あせることなく、日本人の心の本質をとらえており、いまだに多くの高校の現代文の教科書に載っています。
その内容を大まかに説明します。
人間の価値には、「である」価値と、「する」価値の二つの価値があります。「である」価値の一番分かりやすい例は、「王様である」という価値です。

一方の「する」価値とは、例えば、社長「である」ことに安住して何も「しない」でいると、いつかは社長の座を追われかねない、ということです。既成の権威はあらゆる角度から検証され、無為は無能とみなされます。そして丸山氏は、江戸時代の身分制度(まさに「である」価値観)が崩壊し、近代西欧を模倣した能力主義(「する」価値観)が浸透してゆくにつれて、明治から昭和にかけての日本には、本来「である」価値観が尊重されるべき領域に、猛烈な勢いで「する」価値観が蔓延して、恐るべき「価値倒錯」が起こったと指摘しました。丸山さんは、この倒錯を再転倒する必要性を説いたのです。



行き過ぎた「する」価値偏重こそが、実は近現代の日本の成長・発展の源であるのかもしれません。しかし、日本とタイは似たように「天皇陛下」と「国王陛下」を、戴く国どうしです。だからもう一度日本人も、タイの人たちの王室や仏教に対するような気持ち、もっと何かを「うやまう」態度を、取り戻す必要があるのではないか、と思いました。