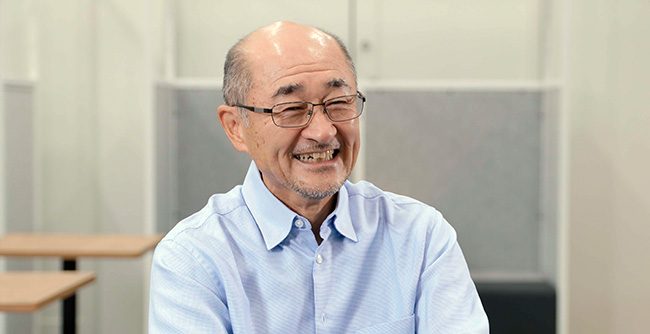生徒や先生、同期の日本語パートナーズとのコミュニケーションで深まる絆
――中学生・高校生の若い人たちと、どのようにコミュニケーションをとっていましたか?
柘植:年代からいうと、我々世代の孫みたいなものですよね。生徒の中には、向こうから積極的にやってきてタイ語を教えてくれたり、差し入れしてくれたりする子もいれば、ちょっと距離を取っている子もいて、日本語パートナーズとしてどういう接し方をするかが一番難しいところでした。私の場合は、自然と打ち解けていくのを待っていた感じです。時間が経てば、彼らも少しずつ慣れてくるものですから。

――現地の先生たちとのコミュニケーションはどうでしたか?
柘植:先生たちとの付き合いは頻繁にありました。若い先生が多くて、家へ帰って自炊する人はあまりおらず、屋台で食べて帰るか、仕事終わりにみんなで食事をする人が多かったです。その時には私も必ず参加していたので、1週間に2、3回は先生たちと一緒に過ごしていました。
――日本語パートナーズ同士のつながりもあったのでしょうか?
柘植:私が派遣されたバンコクの近郊には、総勢10名ぐらいの日本語パートナーズがいました。交通の便がよいところで、年に数回は集まっていたので、同期のみんなとのつながりは非常に強くなりました。
――現地でのコミュニケーションで大変だったことはありましたか?
柘植:授業の時間になっても先生が来ないとか、時間に対する考えが非常におおらかだったのはありますね。
他には、私が派遣された学校はタイ人の日本語教師が3名いたんですが、日本語専門ではなく他の教科と兼務されていたんです。例えば化学の先生をしながら日本語を教えているとか。だから中には、教えている内容にあまり自信がない先生もいらっしゃって、チームティーチングの時、「(ネイティブの日本人がいると緊張するから)今日は来なくていいですよ」と言われることもありました。その時はやっぱりちょっと辛かったですが、お互いの事情を思いやりながら活動することも大切なんだと学びました。

現場へ行くこと、それ自体で何か残せるものがあったと思う
――改めて活動時を振り返って、国際交流で大切だと思うことはありますか?
柘植:交流するにはこうした方が良いとか、あえてあまり考えた事はないんです。ただ、相手と目線を同じにして、相手の立場に立って考えてみることが、ひいては海外の人との意思疎通につながってくると思います。同じ目線で話をすれば、向こうもそれに気づいてくれるはずだし、話もしやすくなる。だから、そんなに肩肘張って交流しようとしなくても、相手も私たちのことを分かってくれると思うんです。
――そういった思いをお持ちの柘植さんだからこそ成し遂げられたということは?
柘植:私にしかできなかったことというのは、あまりなかったような気がしますが、自分がいることで、生徒たちが何か新しい気づきを得てくれていたらいいなと思います。仕事のことや、今までの自分の経験についても話してきましたが、それに対して生徒たちが多少なりとも「そんなこともあるんだな」と興味を持ってくれれば、それでよかったかなと思います。
――冒頭で伺った「アジアの人たちに恩返しがしたい」という思いは叶いましたか?
柘植:約10か月という短い派遣期間でしたから、そんなに大きなことはできなかったと思います。でも、私たちが現場へ行くこと、それ自体で何か残せるものがあったと思うんです。それは、現地の先生や生徒、地域の人たちが、日本人はどんなものかというのを知る意味でも。だから、恩返しになったかどうかは別にして、何かしらやることはできたと思っています。